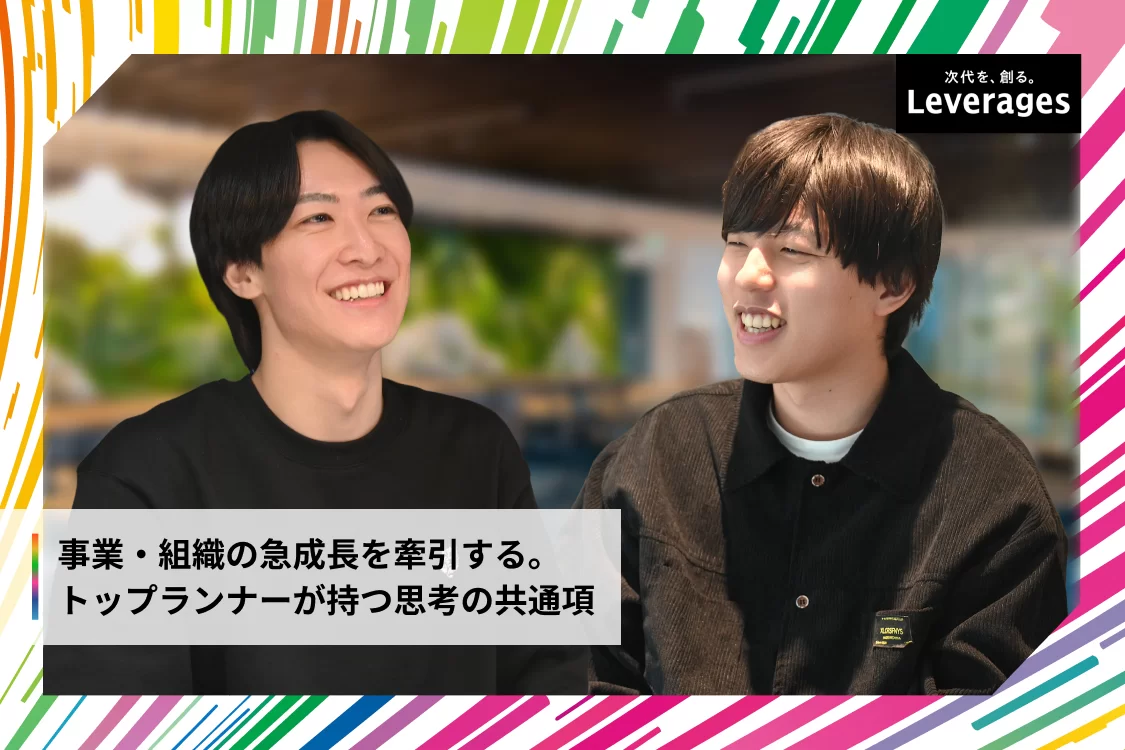マネジメントスキルは武器になる。人事担当役員が語る、キャリア構築の要諦
カルチャー
マネジメント業務は、どうしても”調整役”や”板挟み”といったネガティブイメージを持たれるケースがあります。特に、変化の激しい世の中で「潰しのきくスキル」を求める就活生・若手ビジネスパーソンにとって、必ずしも自分に必要な経験として捉えにくいかもしれません。しかし、執行役員の森口は、早期にマネジメントを経験しておくことがキャリア全体に大きなレバレッジを効かせると語ります。今回は、誤解されがちなマネジメントというスキルの全体像、さらにその先のキャリアパスについて深掘りします。(ライター:丸田)
【Summary】
■マネジメントとは、単なる「管理」ではなく、定量・定性の両面から組織の成果を最大化させるための、再現性のある「スキル」である。
■マネジメントスキルは経験を通じて指数関数的に向上するため、早期に習得することでキャリアの可能性が拡がり、スペシャリストに転向する場合も能力を発揮する土台となる。
■レバレジーズでは、類を見ない事業成長と若手抜擢のカルチャーにより、早期にマネジメントを経験できるチャンスがある。さらに、研修制度や先輩からのフィードバックを通じて総合的に学べる環境が整っている。
-
 森口(Moriguchi)
森口(Moriguchi)
レバレジーズ株式会社 執行役員新卒でコンサルティング会社に入社後、レバレジーズへ2011年に中途入社。メディカル事業本部大阪支店の立ち上げを担当し、リーダー・支店長を歴任。レバウェル株式会社設立を機に執行役員に就任し、全国に拠点展開している事業の統括をおこなう。その後、同社の取締役を経て、2023年7月レバレジーズ執行役員に就任。現在はグループ中途採用と人事戦略、社内制度設計を統括している。
マネジメントというスキルの真の価値
若手ビジネスパーソンにとって、マネジメントというキャリアは市場価値の安定性について不安を感じるケースも多いと聞きます。レバレジーズで人事部門を管掌する森口さんから見ていかがでしょうか?
社内外からマネジメントに関する相談をいただくことは非常に多く、実際に携わる中で「今マネジメントをやってていいのだろうか?もっとプレイヤーとして成長しないといけないのでは?」という悩みを持つ若手も少なくありません。逆に、プログラミングやWebマーケティングのようなわかりやすいハードスキルが人気ですが、実はマネジメントほど安定の蓋然性を高められるスキルは中々ないと思っています。
大前提、市場価値というものは需要と供給のバランスで変動するため、絶対的な安定を保証してくれるものではありません。特定のハードスキルを持つ人材が一時的に人気になるのは、あくまで需要に供給が追いついていないからに過ぎません。しかし、そのスキルセットが普及し、陳腐化すれば必然的に市場価値は下がります。
目先の市場価値に振り回され続けるよりも、人間の普遍的な営みに即したスキルを習得しておいた方が、中長期的に身を助けると考えています。その一つが、マネジメントです。有史以来、現代の会社組織に至るまで「組織を束ね、導き、一人では成し得ない成果を出す」という役割が求められることは変わっていないからです。

なるほど。では、マネジメントとは具体的にどういったスキルなのでしょうか?
マネジメントは、大きく「コトに向き合う」ことと、「ヒト・チームに向き合う」ことに分けられます。
「コトに向き合う」とは、事業のビジョン実現や目標達成に向けて取り組むことです。その中でも、特に数値的な側面を管理・推進するのが「定量マネジメント」です。数値を正しく管理し、現状何がうまくいっていないのか・ゴール達成のために何をすべきかを分析し、具体的な施策に落とし込んで実行する力ですね。一方、「ヒト・チームに向き合う」のが「定性マネジメント」で、いわゆるピープルマネジメントやチームビルディングなどです。
敬遠されている理由は、これらのごく一部である”調整役”や”板挟み”といった印象が先行しているからではないでしょうか。しかし、それはマネジメントの一側面に過ぎません。ビジョン実現・目標達成のためには、まず実現に向けた戦略を描き、戦術に落とし込むことが大前提としてあります。
その上で、戦略を実行するためにメンバーの育成や動機づけをしたり、組織内のコミュニケーションを円滑にしたりすることももちろん重要です。特にAIの台頭によって戦略そのものでは違いが生まれづらくなっている現代においては、こうして実行力を高められるかどうかで成果に大きな差が生まれます。
どの会社にもマネジメントに携わる人はいますが、ロジカルに戦略を描き、成果を残しながら、組織や人の成長も実現できる「真のマネジメント」を高いレベルで実践できているケースは多くありません。そうした観点で、マネジメントとは非常に複雑性が高く、市場から求められ続けるスキルと言えます。
マネジメントスキルを得た先に、どのようなキャリアパスが描けるのでしょうか?
もちろん社内で課長→部長→…と影響範囲を広げていく選択肢もありますし、仮に異業種に転職する場合でも管理職として採用されるケースが多くあります。年齢を重ねていく中で自分の興味のある領域がはっきりしてきたとき、チャレンジの選択肢が増えるというのは大きなメリットなのではないでしょうか。仮に自分で起業するにしても、会社を大きくしていく上でマネジメントは切っても切り離せません。
また、マネジメントの道を歩み続けないとしても、一度経験することでフォロワーシップが高まるため、スペシャリストとしてのキャリアにも活きてきます。実際、弊社にも事業部でマネージャーを務めた後にあえてメンバーに戻ったり、人事など他職種にキャリアチェンジして価値を提供している社員もいます。転職市場を見渡すと、メンバーポジションだとしてもマネジメント経験を求めるような求人も少なくありません。マネジメントを経験したスペシャリストは、リーダーの気持ちや組織運営の苦労を理解できるため、より付加価値の高い仕事ができるんです。
マネジメントの困難とやりがい
実際にマネジメントに携わる上で、どういった難しさがありますか?
ノウハウ自体は世の中に溢れていますが、それを読んだだけでできるようになるわけではないところです。なぜなら、同じ人はいないし、同じ組織も存在しないからです。たとえ同じメンバーで構成されていても、1年前の組織と今の組織は異なります。その中で起きる問題も異なれば、解決すべき課題も異なってくるんです。
私がレバレジーズにジョインし、大阪支店を立ち上げ、支店長を任せていただいた際に、まさにその困難を経験しました。当時の私は、前職や学生時代の経験もあり、知識としてある程度マネジメントはわかっているつもりでした。しかしながら、実際は定性面のマネジメントにおいて足りない部分があったことからハレーションを起こしてしまい、「わかっていることとできることは違う」ということを痛感しましたね。

その困難をどのようにブレイクスルーしたのでしょうか?
支店の仲間に助けられながら、共通の価値観をつくるチームビルディングを行い、組織としての一体感を醸成していきました。そしてチームとして機能していった結果、12ヶ月連続達成に加えて東京を超えて全国で一番の成果を残すような支店になり、多くのリーダー・マネージャー・部長を輩出する組織にまでなることができました。
そのように、自分一人ではなし得ない大きな社会インパクトを生み出せるのはもちろんですし、仲間の成長を見届けることができた瞬間にもマネジメントの大きなやりがいがあります。奇跡的な成果が出たのも、単に私がKPIマネジメントをしたからではなく、一人ひとりが掛け算的に成長していき、全国トップクラスのメンバーまで輩出できた結果でした。そういった心震える瞬間に立ち会えることが、何物にも代えがたい喜びですね。
マネジメント経験を経て、森口さん自身が得られたものは何でしょうか?
一番大きなものは、人としての成長です。もちろん一面的に語れるものではなく、他人と比べるものではありませんが、少なくとも自身だけでなく組織の成果を求め、目の前だけでなく中長期的な視点も持つことができるようになったと感じています。マネジメントに携わることがなければ、今の自分はなかったと断言できます。
人は誰しも自分のためにという欲がベースにありますが、マネジメントを通して本質的な利他性の意味や人格を高めることの大切さに気づきます。これは頭で理解するだけでなく、実際に試行錯誤することでしか血肉に変わりません。

キャリアの可能性を最大化する「早期経験」の価値
とはいえ、若手の中には「まずはじっくり自分自身のスキルを極めてから、おいおいマネジメントに行ければいい」という考えの方もいらっしゃるかと思います。早期にマネジメントを経験することの価値はありますか?
マネジメントスキルは、経験を積むことで様々なパターンを知り、それらが積み重なって指数関数的に向上していくものです。経験が無い中ではイメージしづらいかもしれませんが、根本は勉強やスポーツと変わりません。30歳の時点で実務経験が5年ある人と1年しかない人では、どちらが成果を出せそうかは歴然ですよね。つまり、早くから携わり始めることで経験が蓄積される量が大きくなるので、将来的なキャリアの上限値が高まります 。
「マネジメントをすることでプレイヤーとしてのスキルの成長が止まるのではないか」という懸念もあるかもしれませんが、それは本質的ではありません。マネジメント側に立つからこそ、より高い視座から学び続けたり、複合的な視点から考えたりする必要が生じるため、結果としてよりクリティカルな施策に落とし込めるようになります。さらに、育成を通じて自身のノウハウを体系化して再現性を高められるメリットもありますね。
では、早期にマネジメントを経験するには、どんな環境を選べばいいでしょうか?
大きく2つの条件を満たす会社を選ぶ必要があります。一つは、成長している市場で戦い、かつ事業が成長しているかという観点です。前者は意外と見過ごされがちですが、市場自体がシュリンクしてしまうと事業成長はどうしても頭打ちになってしまうんです。手前味噌ながら、レバレジーズはマーケットインの観点からIT・医療介護・ヘルスケア・保育などといった社会課題の大きい領域で年次120%〜130%の成長を続けているので、新たなポジションもどんどん生まれています。
もう一つ大事なのが、若手抜擢の文化です。たとえ会社が成長していても、年齢を重ねないと任せられない古い体質や、失敗を恐れる文化ではチャンスが回ってきません。レバレジーズは理念の一部にも「各個人の成長を促す*」を掲げ、その抜擢の基準として「信頼」「知性」「情熱」という3つの要素を非常に重視しています。これらを体現し、成果を出している人には、年次・年齢関係なく大きな仕事を任せることで、ダイナミックな事業成長と人材育成を両立し続けてきた歴史があります。今後会社のフェーズが変わっても、その文化はDNAとして変わることはありません。
*レバレジーズの理念:「顧客の創造を通じて関係者全員の幸福を追求し、各個人の成長を促す」

レバレジーズでは、マネジメントを体系的に学べる環境があるのでしょうか?
はい。もちろん任せて終わりではなく、抜擢前後のフォローにも非常に力を入れています。分かりやすいもので言えば、充実した研修制度です。リーダーになる前の「プレリーダー研修」・新任マネージャー向けの「マネジメント研修」など社内で内製しているものに加え、外部の講師を招いたコーチングや、グロービス経営大学院に通う制度など数多く用意しています。
さらに、マネジメントはケースバイケースの対応が多いので、身近に相談できる仲間がいることも非常に重要です。レバレジーズには、若い時期から苦労を乗り越えてきた先輩や上司が多く、実務に即したアドバイスをしてくれるのは貴重な環境だと思います。
さいごに
読者の方々へ、メッセージをお願いします。
この記事を読んでいただいているということは、キャリアに対して何かしらの興味や課題意識を持ってらっしゃるのではないでしょうか。
その中で改めて、マネジメントを食わず嫌いするのはもったいないということを伝えたいです。なぜなら、それは時代や職種を超えて通用する、あなたのキャリアを支える土台となるからです。
レバレジーズには、その土台を早期に築ける環境があります。「想像できない未来の自分に出会いたい」と願うなら、ぜひ一緒に働きましょう!

▼より詳細に取材の様子を収めた動画はこちら▼
▼新卒採用情報はこちら▼

▼中途採用情報はこちら▼