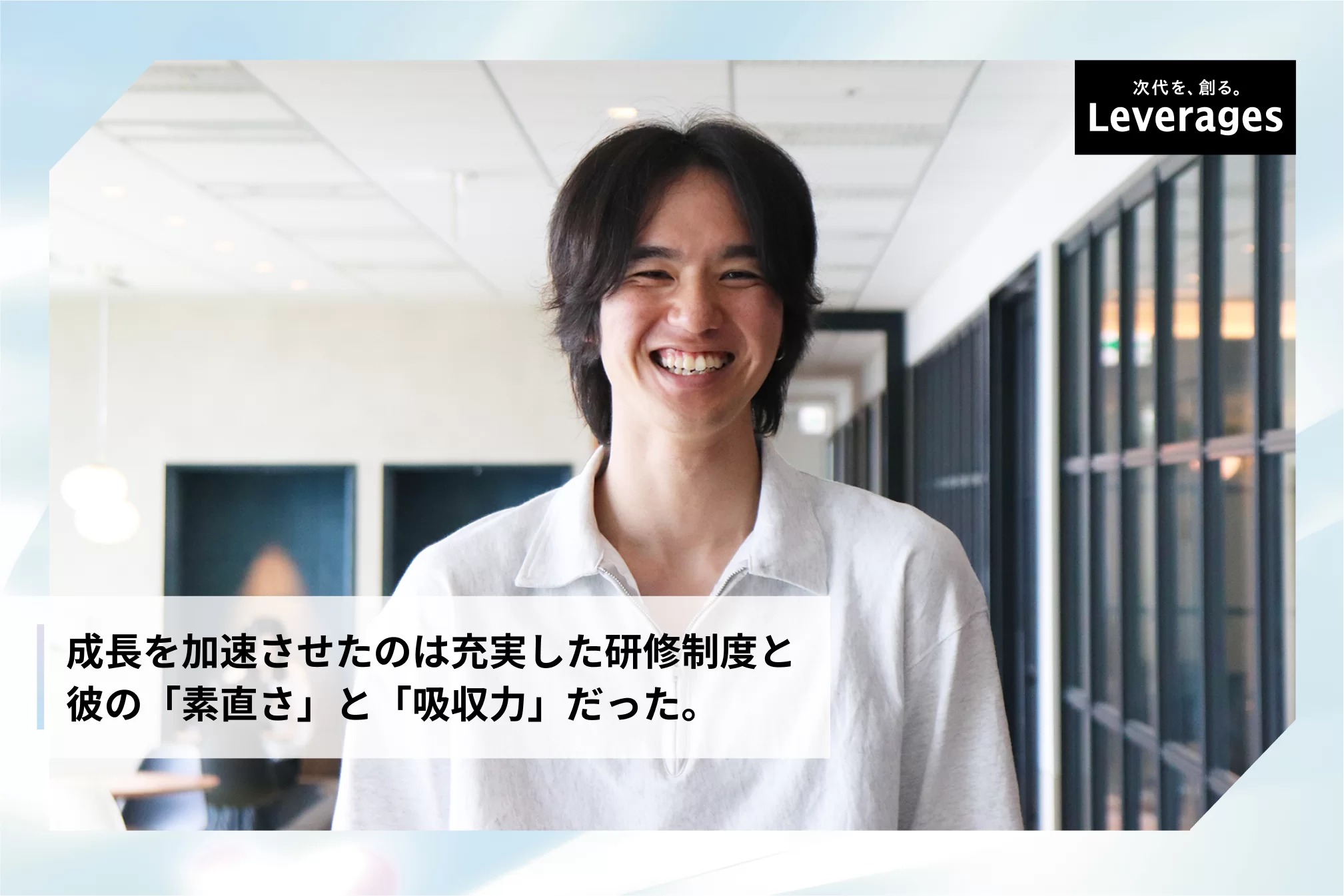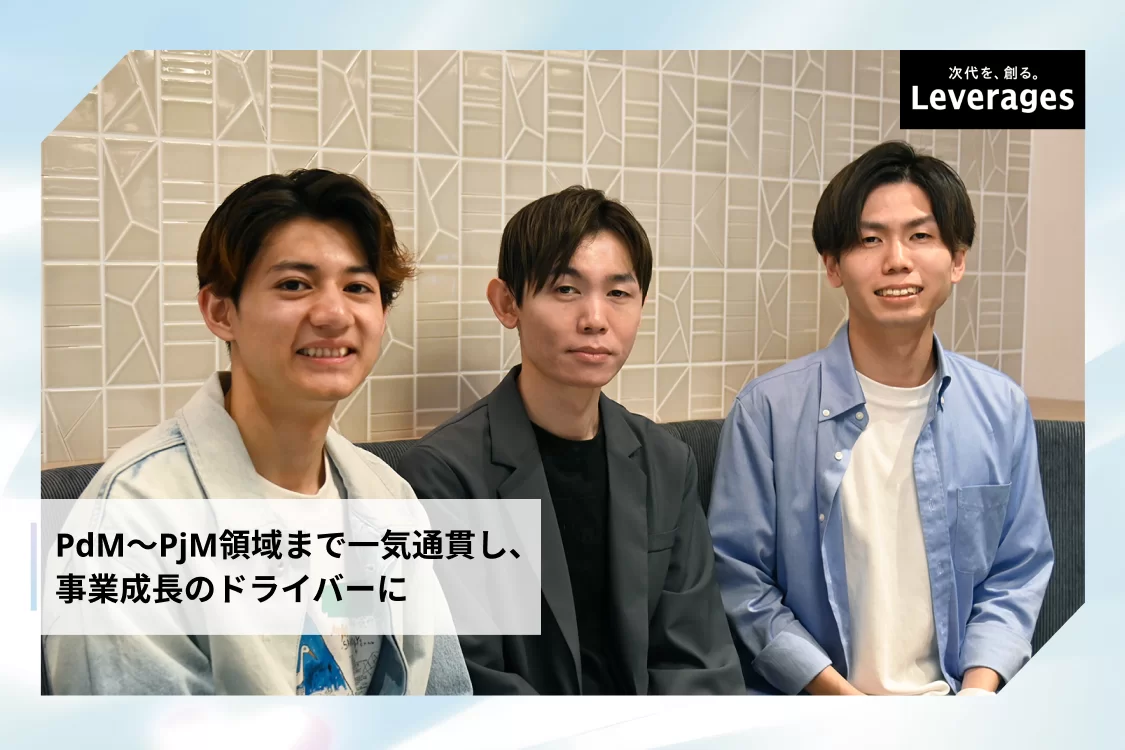QAの専門性を超え、品質改善をリードするプロの仕事術
職種
【Summary】
■大手企業でQAエンジニアとして経験を積むなか、自身のキャリア停滞を懸念し挑戦の幅を拡げるため、立ち上げ期のクオリティアシュアランス事業部へ転職。
■現在は品質コンサルタントとして、テスト領域にとどまらず開発プロセス全体に切り込み、プロジェクトの根本的な課題解決をリード。
■自らの経験を体系化した教育コンテンツを作成し、新メンバーのスキル向上に貢献。チーム全体のボトムアップを図り、事業の成長を推進する。
-
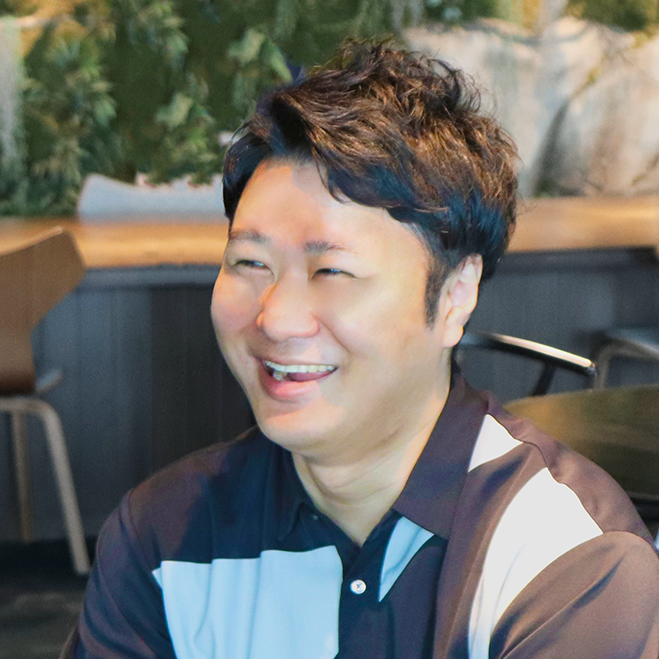 竹内 (Takeuchi)
竹内 (Takeuchi)
慶應大学を卒業後、新卒で学習塾に入社。その後、未経験でIT業界に転身。株式会社SHIFTにてテストリーダー、PMOの経験を経て、2024年5月レバテック クオリティアシュアランス事業部に入社。入社後はQAリーダー・品質コンサルタントとして携わる傍ら、社内教育コンテンツの作成にも従事。趣味はクラフトビール、ラーメン店巡り。
「何でもできる」環境を求めて。大手からベンチャーへのキャリアチェンジ
竹内さんのこれまでのキャリアについて教えてください。
慶應義塾大学を卒業後、新卒で学習塾に入社しました。実は私は、就職活動をほとんどしていなかったんです。大学時代に塾でアルバイトをしており、業務内容が分かっていたのが理由です。結果、入社3ヶ月で違和感を覚え、1年で退職しました。その後、エンジニアの道を探し始めていたところ前職が第二新卒を募集しており、応募したのがIT業界に入るきっかけです。
前職でのご経験を教えて下さい。
入社後はテスト実行からスタートしました。その後、開発プロジェクトでテスト設計を担当したり、入社2年目からはテストチームのリーダーとして、テスト設計や実行の管理、成果物の管理、そしてお客様とのやり取りをおこなったりしていました。入社3年目からはPMOとしてプロジェクトへ参画し、テストに特化したPMO業務、具体的にはテスト計画の立案、テスト設計のレビュー、テスト実行の管理、不具合に対する管理や分析などを中心におこなっていました。
かなりスピード感を持ってキャリアアップされてきたかと思いますが、QAの分野でキャリアを築いていきたいという考えを持たれていたのでしょうか?
当初からQAの分野に固執していたわけではありませんでした。QAエンジニアとしてテスト設計を突き詰めるよりも、品質コンサルタントやプロジェクトマネージャー(以下、PM)として、より上流からプロジェクトに関わりたいという想いが強かったです。
そんななか、前職でPMOになれたことは非常にポジティブな経験でしたね。PMOとしてプロジェクトの上流から関われるので、将来やりたいと考えていた上流業務とは何か、プロジェクト全体を俯瞰して見るにはどうすればいいかを学ぶ上で良い経験になったと感じています。
転職を考えたきっかけを教えて下さい。
前職で品質コンサルやPMを目指す選択肢ももちろんありましたが、私が退職する前に2年ほどの長期プロジェクトのPMOプロジェクトが決まっており、このままではキャリアが停滞してしまうという感覚が強かったんです。PMになるまでにどれくらい時間がかかるのかという懸念もありましたし、コンサル業務を担当するのは完全に別の事業部だったので、そちらへの異動はかなりハードルが高かったのも実情です。
それでは転職するしかない、という状況だったのですね。当時の転職軸は何だったのでしょうか?
転職活動を始めた当初は明確な転職軸がなかったため、まずはさまざまな企業とカジュアル面談をおこないました。面談を通じて、自身の考えを整理していったかたちです。具体的には、大きく分けて3つの方向性で企業を見ていました。
1.前職よりも事業規模が狭いベンチャー企業
大手のように事業規模が大きすぎると、自分が上に行ける機会が限られていると感じていました。一方で、立ち上がったばかりのベンチャーであれば、コンサル業務、人材教育、組織マネジメントなど、さまざまなチャンスが転がっているのではないかと考えました。
2.外資系企業
自分の市場価値を測りたいという思いがありました。外資系企業と面談することで、自分の需要や市場価値をより客観的に評価できるのではないかと考えました。
3.日系大手SIer
QA中心のキャリアを歩んできた自身が、日系の大手SIerでどのような評価をされるのか、またどのようなキャリアパスを歩めるのかを知りたいと考えました。
方向性の異なる企業と話すなかで、最終的には「自分がやりたいと思ったことに挑戦できる環境」が決め手になりました。特定のキャリアに固執するのではなく、その時々で生まれる興味や課題感に応じて、何にでも挑戦できる環境に身を置きたいと考えたのです。
入社されて、何かギャップはありましたか?
フリーランス事業部やコンサル事業部との横のつながりが想像以上に強かった点に驚きました。入社前は、それぞれの事業部がある程度独立しているものとイメージしていましたが、実際にはレバテック社内の他事業部との連携が非常に多く、多角的な視点からプロジェクトに関われる機会が豊富にあるのは、大きな発見でしたね。
事業部内に閉じこもることなく、自身のアクション次第で影響範囲を拡げていけるだけの文化・環境がレバテックには揃っていると感じました。これは、個人の成長機会を最大化する上でも非常に魅力的だと感じています。

「QAエンジニア」から「品質コンサルタント」へ。プロジェクトの根幹から品質改善をリードする
現在取り組んでいる業務内容について教えてください。
今は複数の大型プロジェクトに携わっています。特に課題となっているのは、本番障害が多発していることや、リグレッションテストの整備が不十分なことです。根本的な原因は、テストそのものが不足している点にあります。
プロダクトオーナー(以下、PO)やマネージャーといった、プロダクトの品質に責任を持つレイヤーの方々は品質を気にされていますが、具体的にどう行動すべきかを示す時間が取れていないのが現状です。また、IT開発現場では開発担当者が頻繁に入れ替わることも多く、品質文化が根付きにくいという難しさもあります。
そのため、まずは私たちQAが「自分たちの価値」を明確に示すことに注力しました。最初のプロジェクトでは、テスト計画を策定し、それに基づいて全てのテストケースを自身で作成。それをエンジニアの方々に実施してもらうという一連のプロセスを実践しました。さらに、出てきた不具合に対して徹底的な不具合分析を行い、不具合が集中している箇所や機能に対しては追加テストを設計・実行してもらい、リリースまで導きました。
このプロセスを通じて「テストはこれくらい必要だ」という基準を示し、品質改善への意識を高めることを目指しました。前職でも同様の業務は経験しましたが、不具合分析から追加テストまで自らが主体的に「切り込んでいく」動きは、当時のプロジェクトではなかなか難しかった部分です。
そのような環境で、現在竹内さんご自身は「切り込む動き」はできていますか?
はい、レバテックではそれが可能です。
次のプロジェクトでは、複数のプロダクトをまたぐシステムのテストPMとして、全体のテスト計画や不具合管理を任されています。遅延している開発チームがあれば、チームのなかに入り込み、朝会や夕会のファシリテーションを自らおこない、エンジニアのタスクアサインも全て担当し、オンタイムに戻すといった、細かなマネジメントもおこないました。チームリーダーには、不具合の直し方の方針検討といった、本来の業務に注力してもらう形で分業しました。
さらに、前職ではできなかったこととして、組織の開発体制やプロセスに問題がないかの分析もおこないました。プロジェクト伴走のなかで見えてきた問題点を洗い出し、それに対する具体的な施策を考え、私たちがどこまでサポートできるのかを含めてお客様に提案し、開発プロセス改善の提案までおこなっています。
レバテックのプロジェクトは、最初の提案時に「品質コンサルティング」として入ることが多く、テストの文脈だけでなく、プロダクトもプロジェクトもすべてスコープになる点が魅力です。プロジェクトが停滞しているとき、それはエンジニアの怠慢ではなく、構造的な問題が潜んでいるケースがほとんどです。そうした場面で、テストという枠組みを超えて品質改善の視点から深く課題解決に踏み込めるのは、レバテックならではの強みです。このスコープの広さは、営業段階から「品質コンサル」として提案しているからこそ可能になっているのだと思います。
自身の経験をコンテンツに。ボトムアップでチーム全体のスキルを向上させる
立ち上がって間もない事業部で、品質コンサルタントの視点を持って業務を進めていく不安はありましたか?
不安はあまりないですね。
知見のあるPMがいるので、困ったことがあっても相談できる環境が整っています。もちろん、プロジェクトのツボを理解するまでには時間がかかりますが、テストPMの延長線上にある業務なので、何度か経験すれば習得できるという手応えがあります。実務を通して経験が積めており、着実にスキルを身につけられている実感があります。
教育コンテンツの作成にも携わられていると伺いました。具体的にどのようなものを作成されたのですか?
入社後にやりたかったことの一つに「教育」があったので、自らコンテンツ作成を志願しました。
具体的には、新しく入社したメンバー向けのオンボーディング資料として、機能テスト以外の「シナリオテストの設計」に関するコンテンツや、SQL、DB、Excel、PowerPointといった、QAエンジニアやIT系に携わる上で実務で使う知識に関する教育資料を作成しました。
前職ではSQLの教育資料が不足しており、新メンバーに私が都度、使い方を教えていました。その経験から、QAとして必須となる知識を誰もが体系的に学べる資料の必要性を痛感し、作成に至りました。
自分で作ったものが実際に事業部内で活用され、メンバーのスキルアップに貢献できているのは大きな喜びです。コンテンツを通じてチーム全体のボトムアップを図り、今後もテスト設計のレビューや、性能テストなどの非機能テストに関する教育資料も作っていきたいと思っています。
これらの教育コンテンツの作成は、竹内さんのキャリアにどのように活かせると考えていますか?
教育コンテンツを作ることは、チーム全体のボトムアップに繋がるだけでなく、私自身のキャリアにも大きく役立っています。
将来、自分がチームや事業部を率いる立場になった際、メンバーの教育に必要なコンテンツを自ら作成し、発信できるという実績にもなります。また、アウトプットする過程で自身の考えが整理され、お客様への提案にも説得力が増すなど、思考がクリアになる効果も実感しています。

会社と共に成長したい人へ。「利他性」を持って、能動的に動ける仲間を求む
レバテックのどんなところが好きですか?
会社のサービスやレバテックの「日本を、IT先進国に。」というビジョンに共感できるところですね。労働問題や日本の社会構造といった社会課題の解決に貢献できる事業に携わっているという実感は、大きなモチベーションになっています。
どのような人と一緒に働きたいですか?
「キャリアを伸ばしていきたい」と強く思っている人に来てほしいです。
コンサルタントやエンジニアは会社の名前ではなく、個人のスキルで勝負する仕事だと考えています。「どこで働いたか」ではなく、「どんな環境であればスキルを伸ばせるのか」を主軸にキャリアを考えている方であれば、レバテックで大きく成長できるはずです。
あとは「利他性のある人」ですね。自分のことだけでなく、チームや組織、そして顧客のために何ができるかを考えられる人であれば、レバテックで大きく成長できるはずです。お客様のプロダクトをより良くするという意味での利他性はもちろん、社内のメンバーに対しても積極的に情報共有し、助け合える。「事業を自分たちで作っていく」という当事者意識を持った方だと嬉しいですね。
規模の大きな組織では、マネジメントなどの上流工程は経験豊富な中途入社者が担うことが多く、若手がそのポジションにたどり着くには時間がかかることもあります。しかし、今のクオリティアシュアランス事業部であれば、意欲次第で様々なことに挑戦できます。QAの専門性を深めるだけでなく、マネジメントなど多様なチャレンジをしたい人には、非常に良い環境だと思います。
今後のキャリア展望について教えてください。
具体的なキャリアパスはまだ決まっていません。
品質コンサルとして専門性を高めていく道もあれば、PMとしてプロジェクトを推進する道、あるいは事業部の教育担当としてメンバーの育成に貢献する道も考えています。もちろん、それら全てを包括的に手掛けることもできれば、とも思います。
今は、レバテックでできること全てを全力で経験し、自分の可能性を最大限に伸ばしていきたいと考えています。明確なキャリアパスが決まっていないからこそ、さまざまなことに挑戦し、一番伸びたところに注力していく。もし何か一本やりたいことが見つかった時にも、幅広い選択肢と経験が活かせる環境だと感じています。
最後に、これからレバテックへ入社する方に向けてメッセージをお願いします!
レバテックは、テストの枠を超えて「品質」という大きなテーマに深く関われる環境です。
能動的に動き、新しい知識を吸収し、常に自分をアップデートしていける方であれば、きっと大きなやりがいを感じられるでしょう。チャレンジさせてくれる風土があり、困った時にはサポートしてくれる仲間もいます。私たちと一緒に、日本のIT業界の品質向上に貢献していきませんか?
▼現在募集中のクオリティアシュアランス事業部の求人はこちら!▼