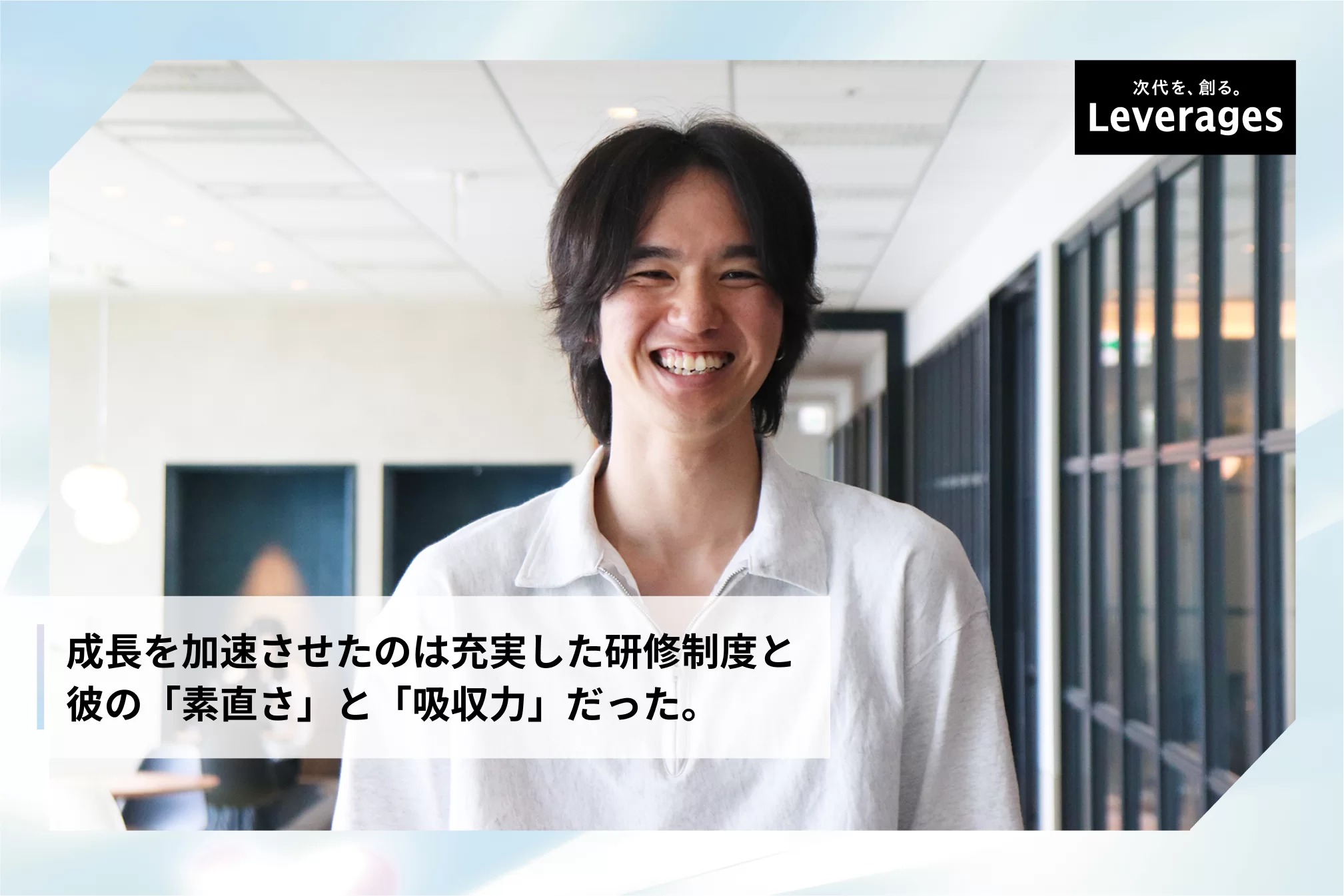日本を代表する大規模プロジェクトのPM出身者が考える、事業成長に貢献するシステム開発とは。
職種
今回のインタビューでは、レバテック執行役社長の泉澤が聞き手となり、藤咲さんのキャリアにおける重要なターニングポイントを深掘りします。
長年レバテックの成長を最前線で牽引してきた泉澤だからこそ引き出せる、CTO室にジョインした藤咲さんの内なる想い、そしてレバレジーズで描く未来とは。どうぞご期待ください。
大手SIerから創業期ベンチャー、そして外資系大手を経て、レバレジーズへ入社した藤咲さん。多様な経験を通して見えてきたのは、日本のSIerが抱える構造的な課題。
事業戦略と開発の間に存在する受発注の壁を打破し、真にビジネスに貢献できるシステム開発の実現を目指し、2024年7月、藤咲さんはレバレジーズへと新たな一歩を踏み出しました。
それぞれの決断の背景にあった想いや、そこから得られた学び、そしてレバレジーズで描く未来について、熱い想いを語っていただきました。
(ライター:青木)
-
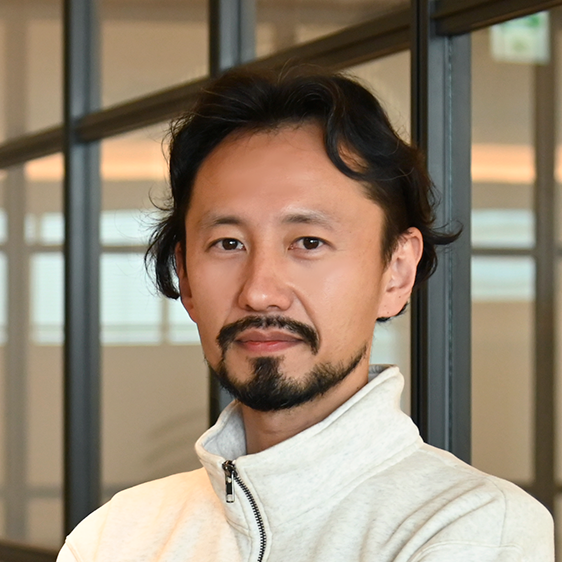 藤咲(FUJISAKU)
藤咲(FUJISAKU)
レバテック CTO室2006年にTIS社に新卒入社。2012年5月に当時創業期であったSHIFT社に参画。
その後、日本IBM社に入社。2024年7月、レバレジーズに入社し、レバテックのCTO室にジョイン。
趣味はランニング、ラグビー観戦、動画編集、お酒。 -
 泉澤(SENZAWA)
泉澤(SENZAWA)
レバテック 執行役社長2017年、新卒でレバレジーズ株式会社に入社。
新規事業の責任者として、IT特化型就職支援サービス「レバテックルーキー」や、プログラミングスクール「レバテックカレッジ」を立ち上げ、事業の基盤を築く。
2021年、レバテック ITリクルーティング事業部部長に就任し、事業戦略の立案、採用、業務最適化を推進し、複数ブランドの成長を多角的に牽引。
2023年4月にレバテック執行役員に就任し、2025年4月1日付で執行役社長に就任。
挑戦と成長を求めて -藤咲さんのキャリアを彩るターニングポイントとは


泉澤:まずは、藤咲さんの今までのキャリアについてお聞かせください。
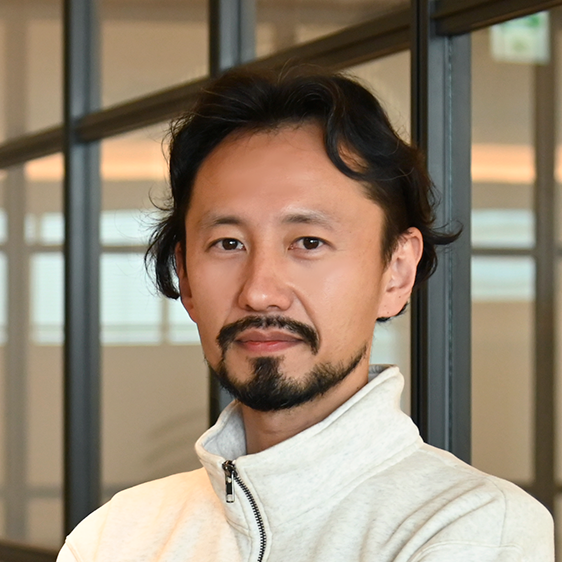
藤咲さん:2006年にTIS社に新卒入社し、1000人月規模の大規模ウォーターフォール案件からBIシステム、スクラッチ開発によるWebアプリ開発まで、要件定義から運用保守に至る全工程を経験しました。その後、2012年5月、約30人規模の創業期であったSHIFT社に参画。SHIFT社ならではの価値提供を模索し、それを武器に事業成長を推進することに尽力していました。SHIFT社での2年間の経験を経て、日本IBM社に入社。当時黎明期であった、アジャイル開発の日本への普及に従事。そして2024年7月、レバレジーズに入社しました。

泉澤:創業期のベンチャー企業に飛び込むきっかけは、何だったのでしょうか?
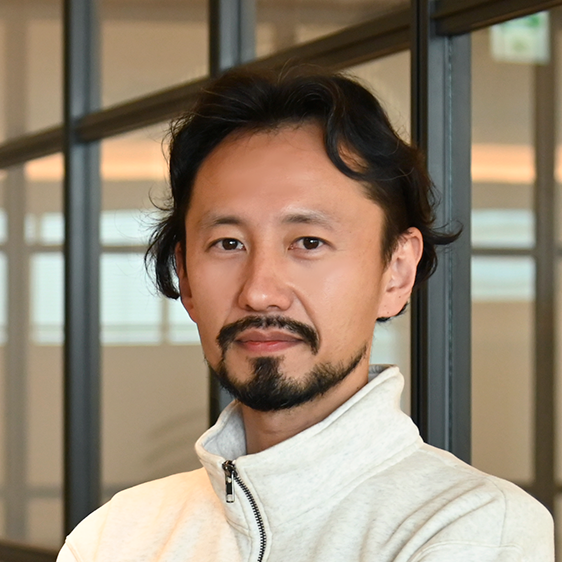
藤咲さん:入社5年目頃のビジネススクールでの学びをきっかけに、自分のキャリアに焦燥感を覚えるようになりました。それまでの私は、目の前の案件を「こなす」ことにフォーカスを置いていて、「事業成長」や「顧客への本質的な価値貢献」というような、ビジネス観点が欠如していたことに気づいたんです。
そこで、自分なりに顧客ニーズを汲み取り、社内で新たな提案をしようと挑戦していたんですが、超大手大規模SIerの受託開発という立場ゆえの壁に度々直面しました。重厚長大なプロセスを遵守する必要があり、それによってコストが膨らみ、顧客のニーズとのギャップが生まれなかなか提案が通らないという状況が続いていたんです。
今振り返れば、顧客ニーズに応えるためのより良いアプローチは他にもあったかもしれません。しかし当時の私には、顧客視点で深く思考する機会も、そのための思考力や視野も不足していたのだと痛感しています。

泉澤:その後転職先に、当時創業期であったSHIFT社を選んだ理由をおしえてください。
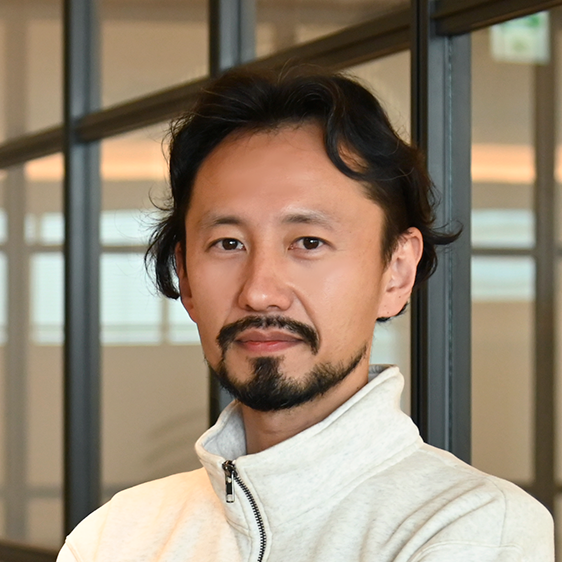
藤咲さん:既存の枠にとらわれず、0→1でビジネスをつくり上げていく経験をしたかったからです。具体的には、前職での課題感から顧客への本質的な価値貢献ができるビジネススキームの構築ができる環境を求めていました。
決められたプロセスをこなすだけでなく、自らビジネスを創造し貢献できる環境に大きな魅力を感じ、チャレンジングな決断でしたが飛び込む事を決意しました。
入社後は実際に、会社としてより大規模な案件獲得を目指し、自社の競合優位性をどう構築するか、顧客にとって最適なオファリング(※1)は何かを模索しながら「事業を伸ばす」ための戦略を構築する、入社前にまさに求めていた経験が叶いました。

泉澤:SHIFT社でオファリングやビジネスの上流を経験し、自信や自負も付いてきたと思います。そんななか、超大手外資系企業である日本IBM社に転職を決めたきっかけはなんだったのでしょうか?
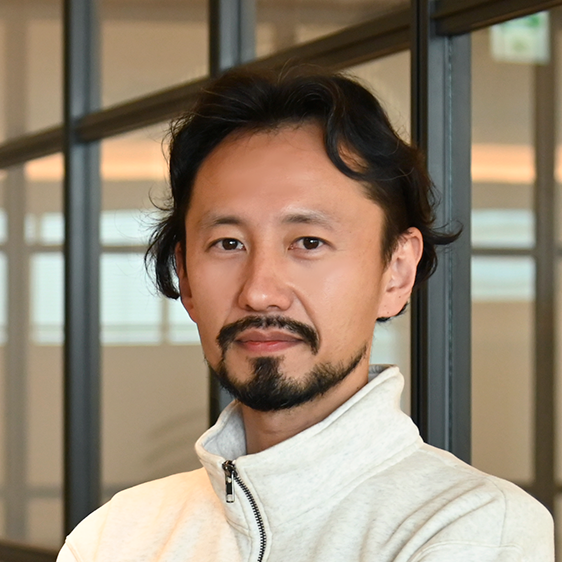
藤咲さん:案件で出会った日本IBM社のプロジェクトマネージャー(以下、PM)のマネジメントレベルの高さに驚き、自分もこの環境でスキルを磨きたいと考えたのがきっかけです。
それまで見てきたPMの方たちや自分が思う優秀なPM像は、いかにプロセスに滞りが無いように回すことができるかが重要だと思っていました。しかし、IBMのPMは想像の域をはるかに超えたPM力があったんです。
日本を代表するような企業の大規模プロジェクトを回すにあたり、プロジェクト単位だけでなく各ステークホルダーのマネジメントまで完璧にこなしていく。IBMのPMのレベルの高さは業界内でも評価が高く耳にしていましたが、その卓越したマネジメントを目の当たりにし、同社に脈々と受け継がれる文化やノウハウを吸収することで、自身のスキルをさらに高めたいと強く感じました。
※1 顧客の課題やニーズに合わせ、技術やソリューションを組み合わせたパッケージを提供すること。
黎明期であったアジャイルを日本に浸透させる

泉澤:日本IBM社で取り組まれていた業務について詳しくお聞かせください。
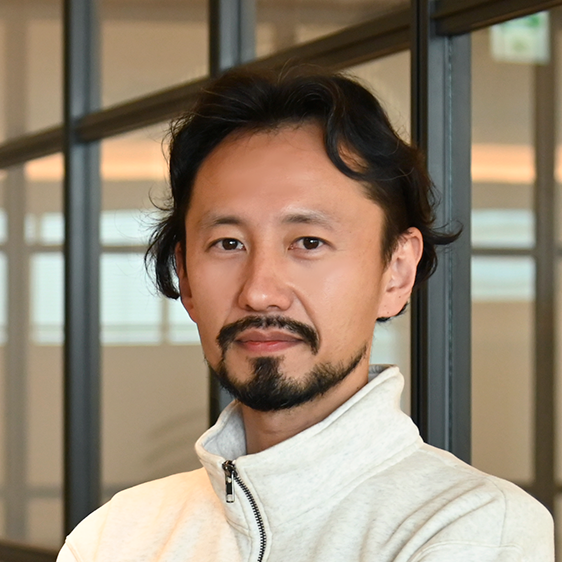
藤咲さん:日本IBM社では、グローバルでの品質改善のノウハウや技法・ツールを生かしたコンサルティングと、当時黎明期であったアジャイル開発を日本に根づかせる取り組みをおこなっていました。
日本IBM社では、創業期のベンチャーとは異なる大規模ビジネスへの対応が求められます。そのため、アジャイルを日本に浸透させるには単なるコーチングではなく、CoE(Center of Excellence)と呼ばれる組織横断の仮想組織を立ち上げ、事業と開発が一体となった開発体制を構築し推進するための様々な企業レベルでの問題解決をおこなう必要がありました。これは事業会社とITベンダーが協業し、さらに多くの開発会社が工程ごとに関与しシステム開発をおこなう、という日本独特の商流の問題が大きいです。内製化比率の高いグローバルでは問題になりづらいですが、日本のビジネスモデルにおいては受発注契約や予算管理、人材不足などの問題にも対処していく必要がありました。

泉澤:日本独自の取り組みを、藤咲さんが推進されていたんですね!
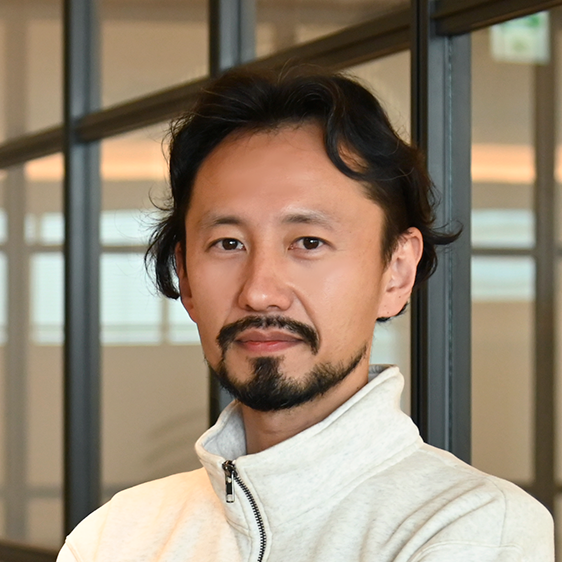
藤咲さん:そう言っていただけると光栄です。ただ、格好よく言えばそうですが、グローバル企業という環境下では、日本特有の複雑な問題解決に率先して取り組もうという人材は、必ずしも多くはなかったのかもしません。だからこそ、挑戦の余地と大きな意義を感じていました。
そのほかに、大規模アジャイルフレームワークであるSAFe(※2)の導入にも注力していました。これは、日本の名だたる大企業のお客様に対してアジャイルの推進をおこなうには、小さな1チームのアジャイル開発のみでは問題が解決できないことも多いために導入を進めました。
※2 大規模な組織でアジャイル開発をスケールさせるためのフレームワークの一種。 複数のチームが連携し、経営とITが一体となってビジネス価値を迅速に提供する。
多様な経験を通して見えた、日本のSIerが抱える構造的な課題


泉澤:創業期のベンチャー企業、超日経大手、外資系大手など、さまざまな業態でご経験を積んだからこそ分かった、現在の日本のSIerの課題はなんだと考えますか?
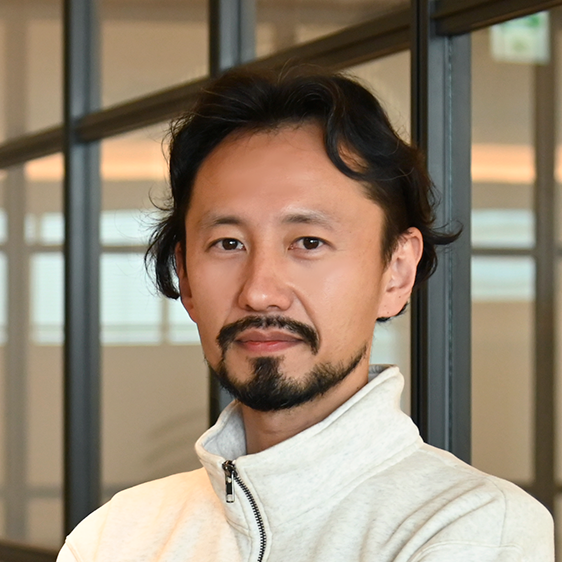
藤咲さん:日本の大規模システム開発を支えてきたVモデル開発は、これまで多くの成功や失敗を繰り返し、知見や経験を積み重ね洗練させてきたという背景もあり、多くの現場で採用されています。しかし、目まぐるしく変化する現代のビジネス環境において、事業戦略と開発を真に連携させ、迅速かつ柔軟なシステム開発を実現しようとすると、従来の受発注の枠組みや開発モデルでは限界があるのが現実です。

泉澤:事業戦略と開発を真に連携させるためには、Vモデル開発では実現が難しいのはなぜなのでしょうか?
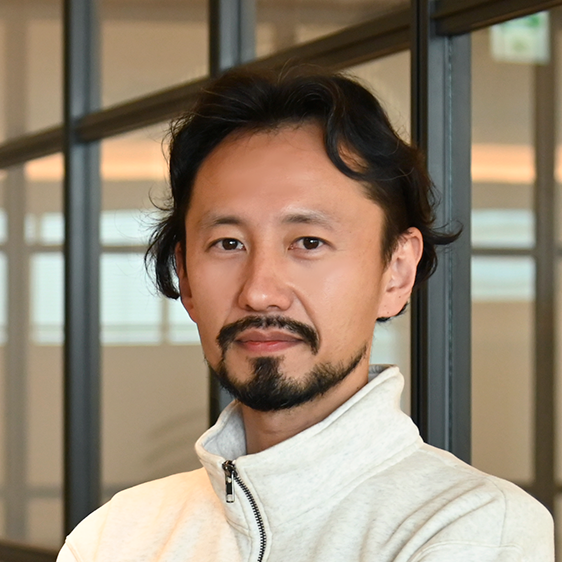
藤咲さん:Vモデルが前提とするのは、要件定義段階でのスコープの定義と、その後のフェーズにおける大幅な変更の抑制による手戻りコストの削減です。しかし、事業戦略は市場の変化や競合の動向、技術革新など、予測不可能な要因によって常に変化し続けます。その変化に追随するためには、開発側も柔軟に方向転換し、迅速に実装していく必要があります。
現在の受発注の枠組みにおいては、どうしても契約で定義されたスコープと納期が絶対となり、その枠内での最適化が優先されがちです。事業戦略が途中でピボットした場合でも、契約変更の手続きや追加コスト、納期の遅延といった課題が立ちはだかり、結果として、真に事業に貢献するシステム開発が阻害されてしまうことがある。事業戦略に基づいた本質的な開発を進めるには「契約」や「受発注の関係」でなかなか実現化するのが難しい状況にあると感じました。

泉澤:なるほど。今のお話を聞くと、藤咲さんが日本IBM社時代に推進されていた、「アジャイル開発」はその状況を打破しうる存在なのではないかと感じました。
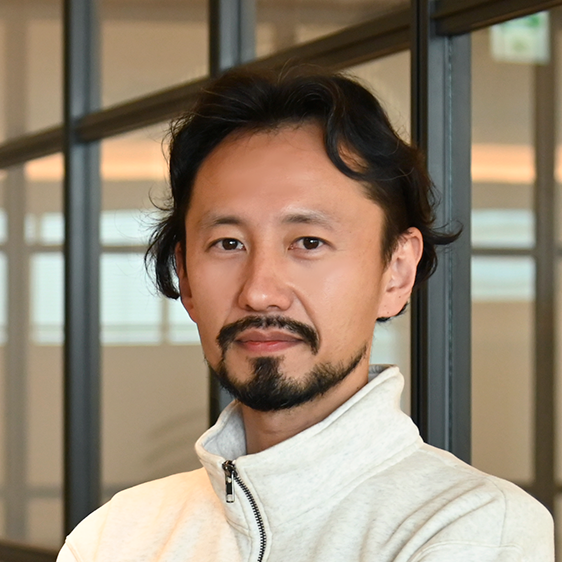
藤咲さん:ビジネス戦略に真に根ざしたシステム開発を実現するためには、変化への適応力と迅速な価値提供を重視する開発アプローチが、現時点での最適解に近いと考えています。
しかし、SIerのビジネスモデルにおいては、アジャイル開発の導入は容易ではありません。クライアントとの間で長年培われてきた受発注の関係性が、アジャイル開発やSAFeが求める柔軟性や協調性を阻害する要因となることは少なくないからです。

泉澤:質的に事業戦略と紐づいた開発を進めるとなると、受発注の壁を壊すのはとても難しい状況なのですね。
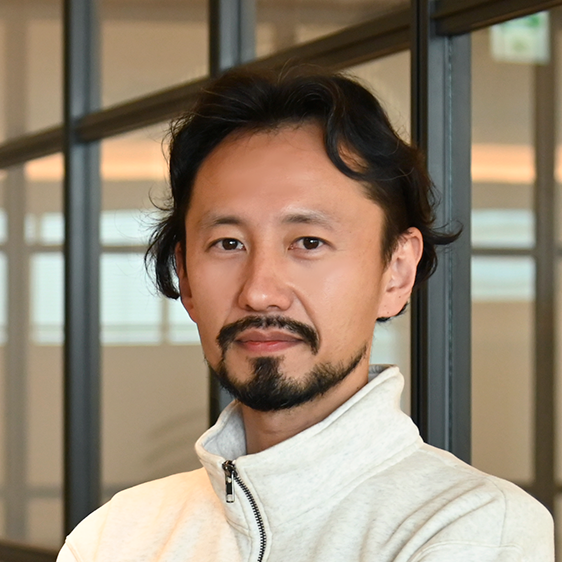
藤咲さん:今の日本のSIerのビジネスモデルでは、すぐに実現させるのは困難な印象ですね。
だからこそ私自身、事業に一番近い事業会社の開発部という立場で、事業戦略や経営戦略に紐づく開発を実現したいという想いが芽生えてきたのかもしれません。
レバテックとの邂逅、共鳴したビジョン


泉澤:藤咲さんはリファラルで入社をされていますよね。カジュアル面談を受けた当初は、転職する気はなかったと聞きました。
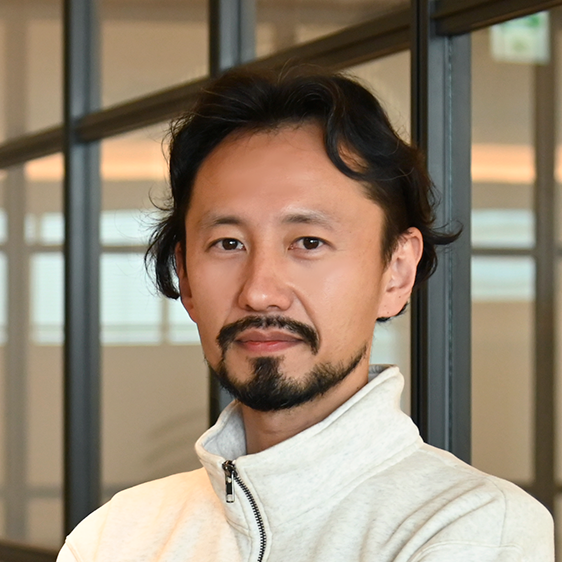
藤咲さん:SIerで働きながらジレンマや受発注の壁を感じつつも、日本を代表するような企業での大規模案件に携わることで社会へ貢献や自己成長に繋がっている実感を得ることができていたため、自身のキャリアとしては順風満帆で転職も考えていなかったんです。
そんななか、友人の紹介でレバレジーズのカジュアル面談を受けたのですが、面談を経るうちに自分の潜在的なニーズに気付かされました。
コンサルタントの役割は事業会社の最終意思決定を支援することで、事業の成果に対する投資対効果は、当然ながら事業会社が責任を負うべき範疇です。しかし、数多くのプロジェクトで変革を推進する中で、拭いきれない問いに突き当たるようになりました。「このまま、誰かの意思決定を後押しするだけで、本当に自分の力を最大限に活かせているのだろうか?」「事業の成長に直接関われないことに、心のどこかで物足りなさを感じているのではないか?」「自らの意思と判断で事業を動かし、その結果にまで責任を負う。そんな環境と立場で、自分は挑戦したいのではないか?」と。
そうした自問自答を繰り返すうちに、事業会社のPMとして、自らの意思で舵を取り、その結果に責任を持つというキャリアに、強く惹かれるようになったのです。

泉澤:転職を考えていない状況だったところから、なぜレバレジーズへ入社を決めたのか。その理由をおしえてください。
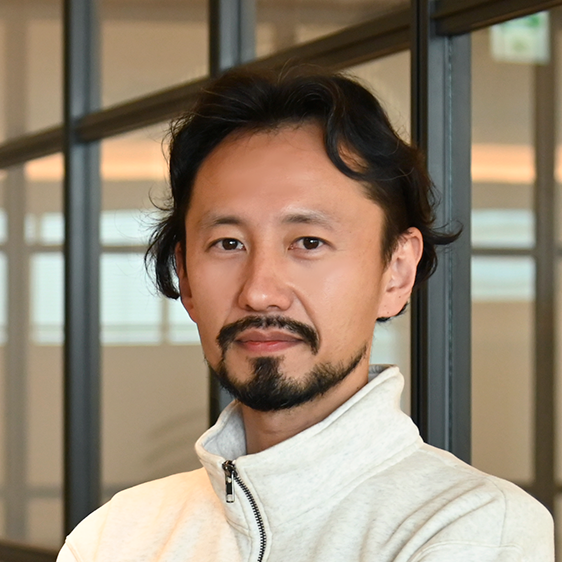
藤咲さん:「日本を、IT先進国に」というビジョンへの強い共感が大きな理由です。
外資系SIerで働いていると、日本がまだまだIT後進国であることを痛感することが多くありました。特に日本は前述したように、直接的にビジネス貢献ができる本来実現するべき開発体制を実現することが難しい状況です。私はその状況をアジャイルの普及というアプローチで解決を目指していましたが、別のアプローチで解決を目指していたのが「レバテック」だったんです。
人材事業・メディア事業・コンサルティング事業・品質保証事業、などと包括的な側面から、本気で日本をIT先進国にするために奮闘している組織に大きな魅力を感じました。

泉澤:組織構成や開発体制において、魅力に映った点はありましたか?
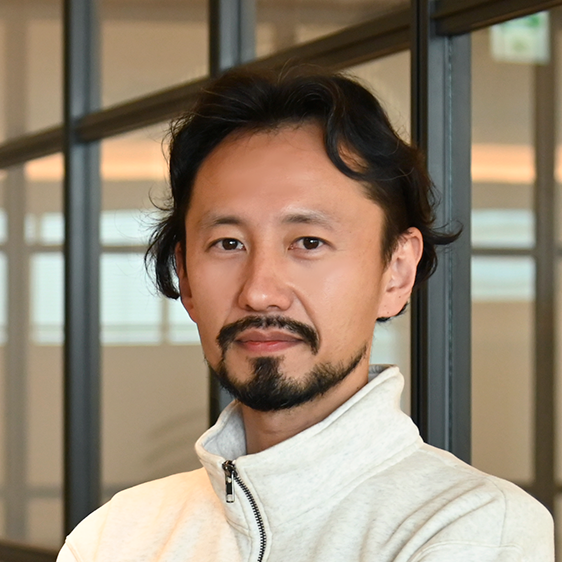
藤咲さん:事業部と開発部が一体となって、事業戦略に紐づいたシステム開発を、アジャイルを使って進められる体制が、大きな魅力だと感じています。
入社前に、レバテック代表の泉澤さんや開発部長やマーケティング責任者と話をするなかで、開発部と経営層との距離の近さや関連部署との距離の近さを感じました。また、レバレジーズはオールインハウスの体制で、セールス・マーケター・エンジニア・デザイナーのスペシャリストが社内に在籍している。これだけの要素が揃っていたら、これまでSIerやコンサルタントとして様々な案件に参画してきた経験から見ても、比較にならないほどの速いスピード感でシステム課題の解決に取り組むことができるのは明らかです。
「言われたものを作る」のではなく、「ビジネスを成長させるためのシステムを自らの手で創り出す」ことを、この会社なら実現できるポテンシャルがあると思いました。

泉澤:レバレジーズの組織体制であれば、経営戦略に紐づいたシステム開発ができる可能性があるということですね。
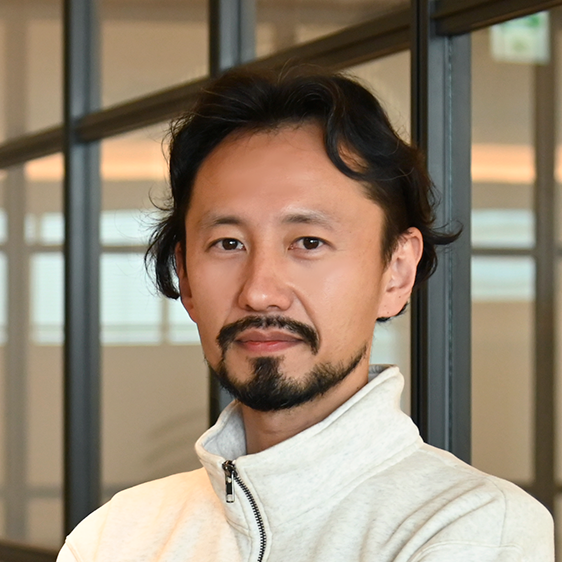
藤咲さん:これだけの要素が揃っていたら、実現できる可能性は大いにあると思います。その根拠として、レバレジーズの独立資本経営の体制に大きな要因があると考えてます。
多くの企業では、開発部に割り当てられた予算の中で何ができるのか、あるいは余った予算で何を開発しようかという、予算の範囲内でできることを模索するケースが多いです。しかし、レバレジーズはその逆です。今のシステム課題を解決するためにはどれだけの予算が必要なのかを考えた上で、必要な予算がしっかりと付きます。
会社や事業を成長させるためにシステム開発をおこなうという、本来あるべき考え方が、この会社には深く根付いていると感じています。
さいごに


泉澤:さいごに、どんなPMの方と一緒に事業を推進していきたいか、おしえてください。
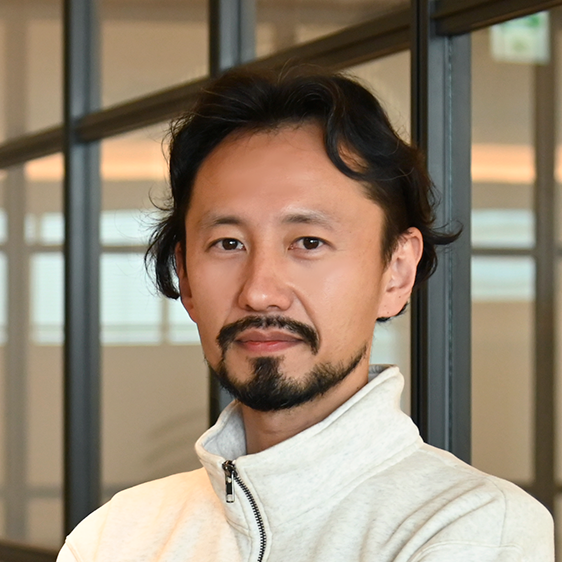
藤咲さん:レバレジーズの事業をシステムの力でいかに成長させるか。技術選定、事業部門との連携強化、メンバーの育成、そして新たな才能の発掘といったあらゆる手段を戦略的に考え、実行できる方と共に、未来を創っていきたいですね。
レバレジーズのエンジニアは学習意欲と責任感が強く、自分たちの業務に誇りを持っている人が多いです。障害対応時には事業継続のために最後まで粘り強く対応を続ける開発チームばかり。事業部門のユーザーもその姿勢を理解し、共に問題の解消を最優先におこなう姿勢は、まさにレバレジーズの強みです。また、多くのエンジニアが技術ブログで積極的に情報発信をおこない、社内外の勉強会にも積極的に参加しています。
一方で、若さと勢い、そして真摯に業務へ取り組む姿勢が強いからこそ、時に意見の衝突や、目指す目標・価値基準の揺らぎといった組織的な成長痛ともいえる課題も見えてきました。これは、事業部ごとの意思決定を尊重し、個人の成長を重視するレバレジーズの企業文化ならではの、良い面と表裏一体の状況だと捉えています。
小規模チームの機動力と高い生産性は、レバレジーズの大きな強みです。しかし、今後のさらなる事業拡大を見据えると、さらに事業間の連携を強化していく余地があると考え、現在組織変革を推進している真っ最中です。
システムで事業の急成長を加速させる世界。事業成長を牽引できる開発組織を創り出し「日本を、IT先進国に」という壮大なビジョンを、一緒に実現させましょう!
▼あなたの経験をレバレジーズで活かしませんか?PMポジション募集中!▼