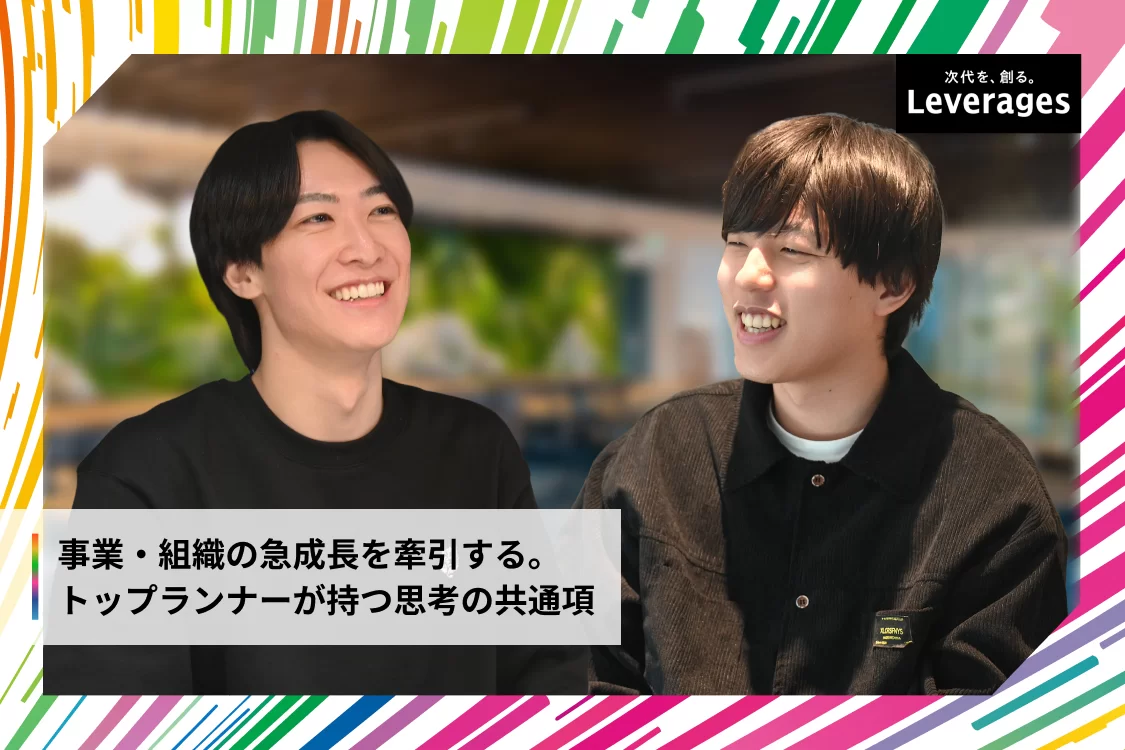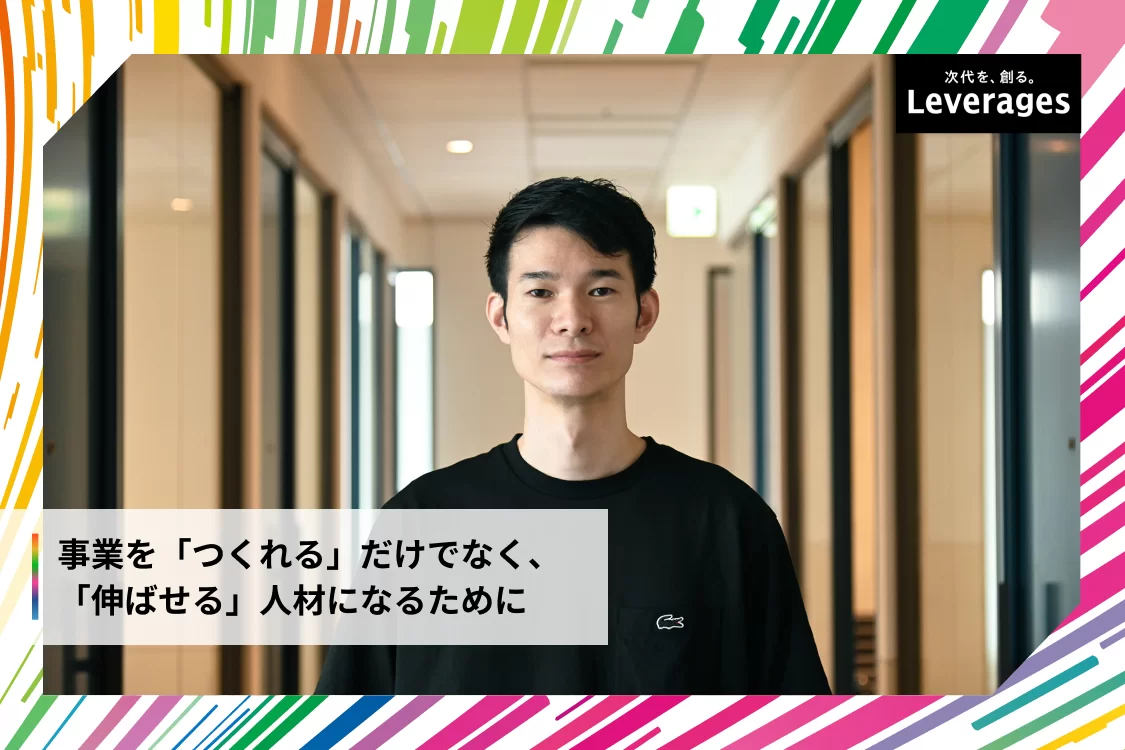
営業経験は遠回りか?事業家を最速で目指すためのキャリア戦略
職種
将来、事業づくりに携わりたいと考える学生にとって、ファーストキャリアは重要な分岐点です。業界だけでなく職種も様々な選択肢がある中で、「営業職は遠回りなのではないか」と敬遠する方は少なくないのではないでしょうか。
しかし、レバレジーズの営業組織は、これまで多数の事業責任者を輩出しています。今回は、営業職としてキャリアをスタートしたのちに複数の新規事業を立ち上げ、現在はレバレジーズ最大ブランド「レバテック」の経営を担う泉澤さんに、事業づくりに求められるスキル・それを得るための環境選びについて伺いました。(ライター:丸田)
【Summary】
■事業づくりには、顧客ニーズから価値を創造する「つくる力」と、事業を成長させ続ける「伸ばす力」の両輪が不可欠。特に、生成AIの台頭によって事業アイデアがコモディティ化する現代では、後者の重要性も増している。
■レバレジーズの営業職は、単なる「モノ売り」ではなく、自らサービスの改善を担う「プロダクトオーナー」である。顧客に最も近い立場でありながら、事業戦略策定から採用・育成までも一貫して担い、事業づくりの能力を総合的に伸ばすことができる。
■レバレジーズの事業に共通するのは「社会課題の解決」。自分たちの仕事が社会に与えるインパクトの手触り感が、日々の働きがいと誇りに繋がっている。
-
 泉澤(Senzawa)
泉澤(Senzawa)
レバテック株式会社 執行役社長同志社大学を卒業後、レバテックキャリアにてITエンジニアの採用支援、キャリア支援に従事。IT人材不足に大きな課題感を持ち、新規事業の責任者としてIT特化型就職支援サービス「レバテックルーキー」や、プログラミングスクール「レバテックカレッジ」など、IT人材を増やす事業を開発。2021年よりレバテック ITリクルーティング事業部部長として、事業戦略立案、採用、業務最適化など、レバテック全ブランドの成長を多方面から牽引。 2025年4月にレバテック執行役社長に就任。
事業づくりに必要とされるのは、「つくる力」と「伸ばす力」
様々なフェーズの事業を運営してきた泉澤さんから、「事業づくりとは何か」、そしてそのために必要な力について教えてください。
事業づくりとは、突き詰めると「ユーザーの課題を解決する営み」です。本来、営業・マーケター・エンジニアといったどんな職種でも、その本質は同じだと思っています。
その上で、実際に事業づくりに携わるために必要な力は、大きく2つに分解できると考えています。市場調査を通じて顧客ニーズを特定し、0→1でサービスを企画する「つくる力」。そして、もう一つが、その事業を1→10、 10→100と実際にグロースさせていく「伸ばす力」です。
一般的に、事業づくりと聞くと「つくる力」をイメージする学生も多いのではないでしょうか。
そうかもしれません。しかし、生成AIの台頭によって調査・企画段階での事業アイデアが差別化しづらくなっている現代では、「伸ばす力」も事業の成否を大きく左右します。どちらかが欠けると限定的な仕事しかできなくなってしまうので、ファーストキャリアではその両輪を伸ばせる環境を選ぶことが重要だと思います。
事業開発の最前線。レバレジーズの営業はモノ売りにあらず

具体的には、どのような環境が望ましいのでしょうか。
両方を高いレベルで経験できる環境は、実は限られています。戦略コンサルなどの支援側だと「つくる」フェーズの一端に関われる一方で実行までは携われないことが多いですし、一人当たりの守備範囲の広いスタートアップでも、実態はトップダウンゆえに意思決定機会に恵まれないケースが少なくありません。そうなると、事業会社の中でも、事業・人材への投資体力があり、若手にチャンスの回りやすい環境が候補として残ります。その中でも、手段に囚われず、ユーザーへの提供価値を突き詰められるポジションを選ぶべきだと思います。
いずれも満たしているうちの一つがレバレジーズの営業職ですが、実は僕自身はそのポジションを一般的な営業職と捉えていません。単なる「モノ売り」ではなく、担当するサービスの「プロダクトオーナー」そのものだからです。
レバレジーズが扱う商材の多くは無形商材です。決まった形がないからこそ、顧客の課題に合わせてソリューションを提案する必要があります。たとえば、HR領域は年単位でトレンドが変わり、顧客が求める価値も変化し続ける中で、サービス自体をアップデートしていかないと生き残ることはできません。つまり、営業一人ひとりが、プロダクトの改善責任を持ち、どうすれば顧客価値が最大化するかを考え、実行する役割を担っているんです。
具体的に、事業を「つくる力」にはどんな要素があり、どのように磨かれたのでしょうか。
まず「顧客のニーズを捉えるスキル」は不可欠で、これがなくして事業が立ち上がることはありません。プロダクトオーナーとして顧客と深く対話していくと、言葉の裏にある本音や、本人すら気づいていない潜在的なニーズを嗅ぎとることができるようになります。その嗅覚こそが、価値ある事業アイデアの源泉になるんです。
たとえば、僕が新卒3年目にプログラミングスクール事業「レバテックカレッジ」を立ち上げたのは、元々エンジニアを志す学生をキャリア支援する「レバテックルーキー」の事業開発の経験がベースになっています。実はこの事業を成功させるにあたって、一番の肝は受講料のプライシングでした。ビジネスモデルとしては、その学生が就職した企業側から紹介料をいただくものだったため、極論受講料は無料で良かったんです。でも、学ぶ途中で学生が離脱してしまったら誰のためにもなりません。
そこで、私はあえて学生から受講料をいただく意思決定をしました。どうしても、人は無料のサービスに本気で自走できないんですよね。もちろん高すぎて負担になってはいけないので、ヒアリングを重ね、彼らの懐事情に対して「これだけ払ったんだから頑張ろう」と思えるラインを探り当てました。言ってみればシンプルですが、そのように背中を押されたいニーズは顧客自身が自覚しているものではありません。机上の調査だけでは辿り着けない、顧客解像度の高さがあったからこそ生まれたアイデアでした。
事業構想がまとまった次には、「多様な職種を巻き込んで形にするスキル」が求められます。社内でマーケティング・ファイナンス・エンジニアなど多岐にわたる職種とコミュニケーションする上で、包括的な知識はもちろん、立場の違う関係者を率いるリーダーシップも得ることができます。レバレジーズはあらゆる専門家を社内に有する「インハウス型組織」なので、部門の垣根を超えて事業を共創する経験は財産になるはずです。

さらに、事業を「伸ばす力」についてはいかがでしょうか。
事業を伸ばすにあたっては、「課題を正しく設定するスキル」・「チームを巻き込んで解ききるスキル」が求められますが、それらはレバレジーズならではの抜擢文化で磨かれました。
一つは、若いうちから大規模な案件を担当できること。大手企業であればベテランが担当するような責任の重い仕事も、レバレジーズでは成果次第で若手に任されます。私自身、新卒1年目に業界をリードしているような顧客を担当させていただきましたが、プレッシャーもある分、数値分析や提案の精度は高まっていきましたね。
もう一つは、早期にマネジメントを経験できること。マネージャーは自ら事業戦略を考えるのはもちろん、それを実行するための組織づくり、さらに採用・育成まで一気通貫で行うことが求められます。ここまでくると、本当に事業開発そのものなんです。このスキルは実践の積み重ねによってしか得られません。だからこそ、レバレジーズの営業組織は事業責任者を多く輩出できているのだと思います。
そうして20代前半で新規事業立ち上げ・現在はレバテック社長として全事業を管掌する経験を積むことができていますが、会社の規模が大きくなった今も抜擢文化は全く薄まっていません。実際、23卒(新卒3年目)で事業責任者をしているメンバーもいますし、それくらいレバレジーズのカルチャーとして色濃く根付いてます。
”下積み”ではなく、現在進行形で社会にインパクトを与えられる環境
レバレジーズの営業組織ではたらく楽しさはどのような点に感じますか?
やはり、「自分たちがこの事業を動かしているんだ」という強烈な当事者意識が持てることですね。用意された商材を横流しするのではなく、その品質を高め、顧客に届け、事業全体の成長に貢献する。そのために必要なことであれば、採用だろうと組織のエンゲージメント向上だろうと、手段を限定せずに取り組める。裁量の大きさと責任の重さが、仕事の面白さに直結しています。
もちろん、顧客の期待を超える価値を提供し続けることは簡単ではありません。求められる基準は常に高く、厳しい場面もあります。しかし、それ以上に、自分たちの仕事が社会に与えるインパクトの手触り感が、日々の働きがいと誇りに繋がっています。
レバレジーズの事業領域は多岐に渡っていますが、共通しているのは「社会課題の解決をど真ん中に据えている」ということです。将来への”下積み”としてのファーストキャリアではなく、現在進行形で自分の仕事が世の中を良くしていると体感できることは、日々の仕事のモチベーションに繋がり、結果として成長も最大化させることができると思います。
さいごに
最後に、ファーストキャリアの選択に悩む学生へメッセージをお願いします!
営業職という選択肢に対して、「ただのモノ売りになるんじゃないか」「会社の一つのピースで終わってしまうんじゃないか」といった不安を抱いている方もいらっしゃるかもしれません。でも、レバレジーズならば、事業の主体者となる経験を積むことによって、市場価値の高いスキルを身につけられると約束します。
何より、ユーザーの困り事を解決する営みは、すべての仕事の基本です。顧客と直接向き合う経験は、将来どんなキャリアに進んでも、あなたのキャリアを支える揺るぎない土台になります。実際、その経験は経営に携わる上でも大いに役立っています。結局は経営もユーザーの課題を解決する手段であり、その変数が事業から人事などに広がっているだけなんです。どこまで上流の仕事になっても、根本の考え方は何も変わりません。
少しでも興味を持ってくださった方は、ぜひ一度私たちとお話ししましょう!心からお待ちしています。