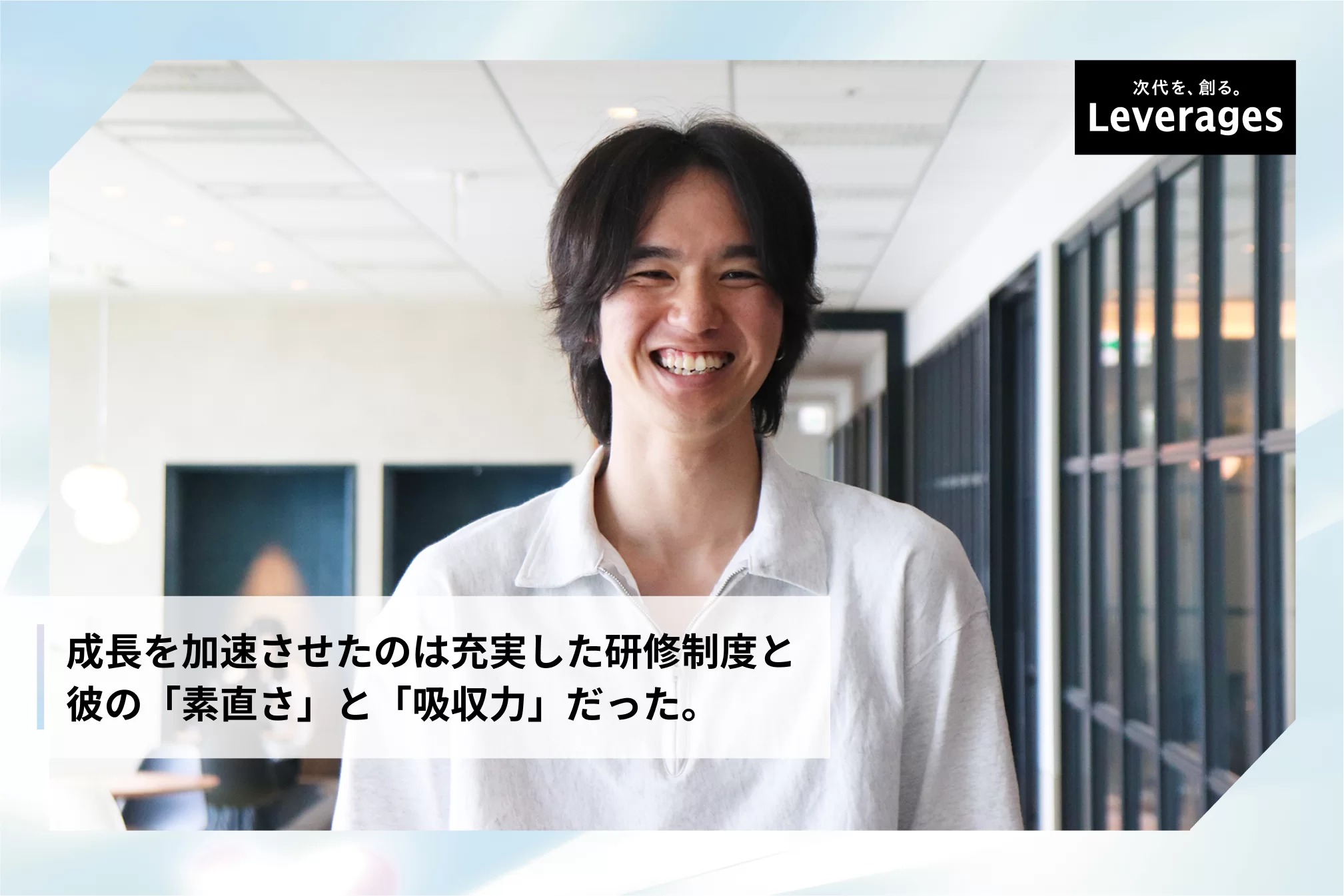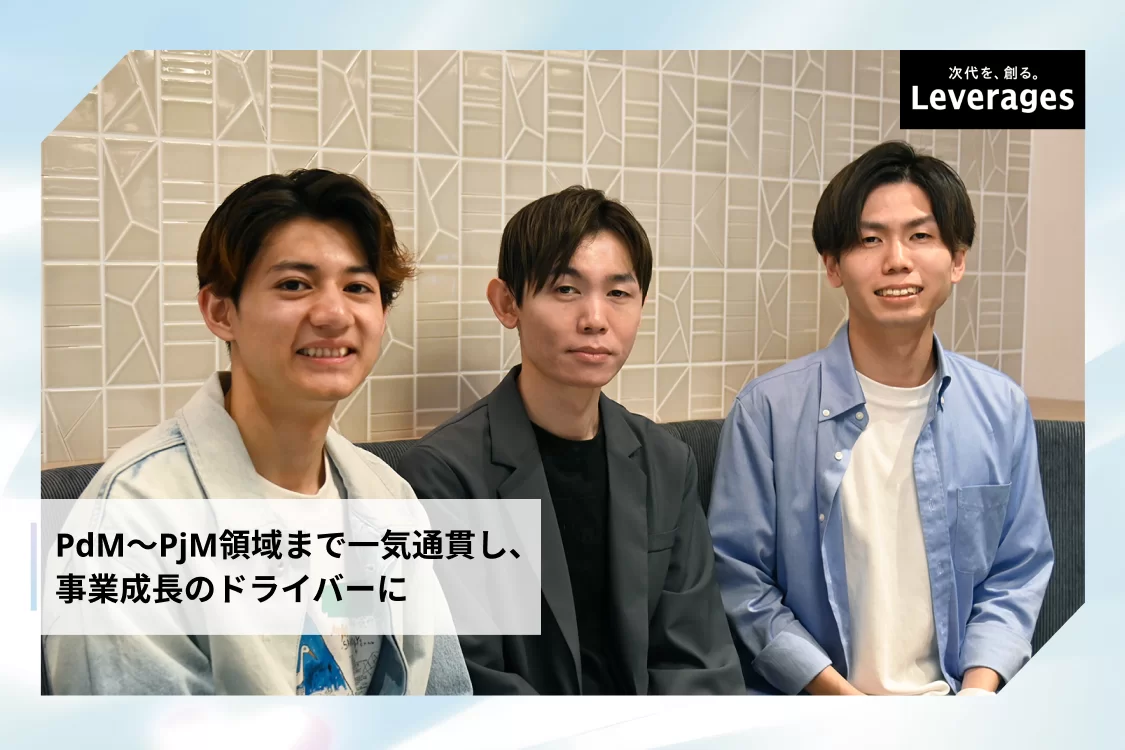「内製化支援」を目標に掲げた、シニアマネージャーの挑戦
外資系大手コンサルティングファーム、事業会社、ブティック系コンサルティングファームと多様な経験を積みレバテックへ入社した松土さん。松土さんの目標は、IT業界の構造的な課題を根本から解決し、クライアントの自走を叶える「内製化支援」を実現すること。レバテックが持つ既存事業のアセットを武器に、0→1フェーズの事業創りにかける、松土さんの情熱と挑戦の軌跡を追います。
【Summary】
■大手コンサルティングファームの「売上至上主義」と「部分最適」に課題を感じ、真のクライアントファーストを実現する「内製化支援」を目指し、未完の地レバテックのコンサルティング事業部へ参画
■未上場で資金調達をおこなわない独立資本経営と、レバテックが持つ既存事業の成功体験を活かし、未完の事業・組織創りに携わりキャリアを最大化
■企画フェーズからプロジェクトへ深く踏み込み顧客と伴走し、クライアントの本質的な課題解決を追求
-
松土(MATSUDO)
コンサルティング事業部 シニア・マネージャー東京工業大学大学院卒業後、アクセンチュア株式会社に入社し、システムコンサルタントとしてキャリアをスタート。その後、金融系の事業会社に入社し、約100億規模のシステム開発を最上流フェーズからリリースまで推進。ブティック系コンサルティングファームでシニアマネージャーとして数々のシステム企画•プロジェクトを支援。2024年のコンサルティング事業部の立ち上げタイミングに、4人目のシニア・マネージャーとしてレバテックに参画。現在はクライアント支援だけではなく、事業開発・組織開発にも従事。趣味は操船&釣り、温泉旅行。

「部分最適」からの脱却。オールラウンダーを志したキャリアストーリー
松土さんはさまざまな業態の企業で経験を積んでいらっしゃいますよね。まず最初に、外資系大手コンサルティングファームのアクセンチュア社から、事業会社への転職を考えたきっかけを教えてください。
アクセンチュア社では、システムコンサルタントとして主にプロジェクトマネジメントに携わっていました。
大手コンサルティングファームの強みと同様、アクセンチュア社も組織の仕組みが確立しており、業務分担が明確です。この環境下で、新人はプロジェクトにおける特定領域の専門性を深め、キャリアを築いていきます。私自身も3年間で多様なクライアントの案件に携わり、専門領域のスキルを深め、貴重な経験を積むことができました。
しかし、3年ほど経験を積むなかで、自分の担当業務が「部分最適」に留まることに気づき、「システムの本質課題の解決のためには、システム全体の最適化を実現する力が不可欠なのではないか」という成長への課題意識を抱くようになりました。
この漠然とした不安をきっかけに、大規模システム全体を最上流の企画・構想段階から下流の実行・運用まで、一貫して手掛ける経験を求め、事業会社への転職を決めました。
事業会社への転職を経験したからこそ得た気づきはありましたか?
コンサルタントとして外側から支援していた時には見えなかった「発注者としてのリアルな課題」を理解できたことが最大の気づきです。
まず一つ目は、100億円規模のシステム更改プロジェクトに情報システム部門のPMOとして参画した際の気づきです。発注側として最終責任を負う意思決定の重責と、決定事項を関係者に理解・周知していくことの難しさを痛感しました。
100億規模になるとステークホルダーは多岐にわたり、社内では役員陣や関係する業務部署、システム部門と連携。また、マルチベンダーとの折衝も求められます。システム開発推進のため、決定した要件をマルチベンダー間で齟齬なく適切に理解してもらい、全体を統率しながらシステム構築を推進するという、外部から支援する立場では負い得ない高度なプロジェクト遂行の統制を求められたことは、事業運営に責任を持つ立場ならではの複合的な難しさでした。
もう一つは、業務部門の異動後に得た気づきです。システム改修や機能追加の要望を出す最上流フェーズを担う業務部門では、実際に業務を担当する人たちが「どういうことで困っているのか」という、現場の肌感覚でしか感じられない本質的な課題感を深く理解できました。
また、業務部門のメンバーはIT知見の高い人が少ないのが現実です。その状況で、直接システム開発を担う部署に要求が投じられる結果、要求が「有象無象」になっているという課題を肌で感じました。
発注者として、大規模システム開発を最上流からリリースまで一貫して担当した経験や、業務部署から要求事項を出すなど、さまざまな立場でシステムプロジェクトに向き合うことができたのは貴重な経験でした。企業が抱えるこれらの構造的な課題を、自分の経験スキルを活かし解決に導き、本質的な価値提供へ還元していきたいと考えたのが、再びコンサルタントの道へ戻るきっかけにもなりました。
松土さんはその後、ブティック系コンサルティングファームへ転職されていますよね。ここでの経験は、松土さんのその後のキャリアにどう繋がりましたか?
「オールラウンダーとしての経験の確立」と「コンサルティング組織の構造的限界の発見」という、その後のキャリアを定める上で重要な二つの視点を知ることに繋がりました。
私が勤務していたブティック系コンサルティングファームは約40人ほどの規模でしたが、集まっていたのは優秀なコンサルタントばかり。システムコンサルティングはもちろん「紙書きの世界」とも言われる、戦略コンサルティング領域も担えるメンバーもおり、真のオールラウンダーが集結していたんです。
私自身も彼らから刺激を受け、日本を代表するさまざまな業界大手企業のプロジェクトに最上流の企画フェーズから参画し、あらゆる業界や領域の課題解決に対応できる経験ができました。アクセンチュア社時代に抱えていた「部分最適にしか携わることができない」という課題意識は、ここで解消されたと言えます。
その一方で「組織として限界」も肌で感じました。優秀な人材を確保し続けられないという採用の壁です。コンサルティングは「人材がすべて」であり、個々の能力がどんなに高くても、優秀な人材を継続的に確保できなければ、組織としてのスケールとクライアントへ提供できる価値に限界が生まれてしまいます。個々の能力が高くても、組織としてのスケールとクライアントへ提供できる価値に限界が生まれることにもどかしさを感じました。
この「個々のプロフェッショナリズムの追求」と「組織の構造的な課題」という両面を知ったことが、後の「レバテックへの入社」という大きな決断に繋がったと考えています。

多くの現場を経験し感じた、日本のIT課題
さまざまな企業で経験を積んだ松土さんが、日本のコンサルティング業界に対して感じる課題をおしえてください。
大手コンサルティングファームの「特化型人材の育成」「売上至上主義」という2つの課題があると感じました。
1.特化型人材の育成による課題
前述したように、大手コンサルティングファームで感じた課題は、経験が一部分に特化しすぎることの危うさです。大規模なプロジェクトでは担当範囲が細分化されているため、プロジェクトにおける「ある1フェーズ」の専門家が生まれます。
その結果「部分最適」は達成されても、「全体最適」が置き去りにされ、結果としてクライアントの真の要望を叶えられないケースが多発。クライアントの事業・組織・システム全体を俯瞰し、本質的な課題解決に導くことができない状況になりやすいのです。
大手ファームでも、ある程度の役職者になると状況は改善される一方で、「全体最適」を目指す経験を積むまでに時間を要するのが現状です。
2.売上至上主義になりかねない組織構造
また、役職が上がるにつれて営業責任を負う必要がある大手ファームの構造は、必然的に「売上至上主義」の構造を生み出します。売上目標達成を優先するがゆえに、最善でないソリューションの提案、または過剰な人員投入など、クライアントの利益を最大化しない選択が下されるケースも少なくないです。
コンサルティング会社に発注をする、クライアント側に課題はないのでしょうか?
クライアント側の視点で見ても、システム開発のアジリティがビジネスの変革スピードに追い付いておらず、システムがビジネスの足かせとなる課題を抱える会社が多い印象です。
これらを抜本的に解決するためにDXの推進が各社で進められていますが、IT人材不足やレガシーシステムの存在、そして経営層の意思決定スピードなど、さまざまな理由でなかなかDXが進まない会社が多いのが実情です。
この状況で外部のコンサルティングファームへ発注しても、内製化ノウハウが社内に蓄積されず、結果的にコンサルタントに頼らざるを得ない「ベンダーロックイン」という負のループに陥ってしまいます。
我々コンサルタントが本来果たすべき役割は、クライアントの根本課題の解決を支援し、将来的には自走できる状態に導くことです。しかし、この複雑な構造的課題が、日本のITの発展を停滞させていると課題を感じました。
レバテックだから実現可能性を感じた、クライアントの「内製化支援」
そのような課題意識をお持ちのなか、リファラル経由でレバテックと出会われたそうですね。同時期に大手ファームからも声がかかっていたそうですが、なぜレバテックへの入社を選んだのでしょうか?
レバテックの「日本を、IT先進国に」というビジョンに共感し、将来的にクライアントが自律的にプロジェクトを進められるよう支援する「内製化支援」の実現を目指す姿勢に魅力を感じたからです。特に、レバテックが持つ2つの組織体制の特徴を理由に、内製化支援を実現できるポテンシャルがあると感じました。
1. 「組織の限界」を解消する強固な人材基盤
前職のブティック系ファームで痛感した最大の課題は、コンサルティング事業における「優秀な人材を安定的に確保できない組織の限界」でした。
これに対してレバテックは、毎年数百名の優秀なプロパー社員を採用できている環境に加え、レバテックの既存事業を通じて数十万人規模のIT人材を保有しています。プロパーとフリーランスとを融合できれば、「人材不足」というコンサルティング事業運営におけるボトルネックを解消できると考えました。
2. 「売上のジレンマ」を解消する独自のビジネスモデル
他社のコンサルティングファームとの決定的な違いは、事業会社としてのノウハウと経営基盤を持っている点です。多くのコンサルティングファームは自社の事業を持たないため、当たり前ですが自社事業における成功ノウハウを持たないケースが多いです。
一方、レバテックには「レバテックフリーランス」や、自社で内製したSaaSシステムなど、50以上もの自社の成功ノウハウが蓄積されており、これらを活用することで、クライアントの課題に対する最適なソリューションを提供することが可能です。
たとえば、IT人材不足には『レバテックフリーランス』の人材基盤を、社員エンゲージメントにはSaaS『NALYSYS』を、生産性向上には『リモピア』を提供することができます。このように、コンサルティングという『点』の支援ではなく、グループのアセットを組み合わせた『面』での根本解決を提案できるのです。
また、通常コンサルティングファームが内製化を支援し、クライアントが自立できるようになると、売上が減少するというジレンマが生じます。
しかし、レバテックには既存事業の安定した収益基盤が存在するため、システムコンサルティングという「点」の売上が減少しても、その他の事業ドメインで恒久的なつながりを生むことで「線」の売上が継続的に発生するため、売上損失のリスクも回避できるのです。
この事業構造により、「内製化支援による顧客課題の解決」と「事業収益の創出」というビジネスサイクルを生み、顧客の本質的な課題解決を実現できると考え、入社を決意しました。
「未完の地」だから得られる挑戦
現在参画されているプロジェクトについて、おしえてください。
現在は大手金融系企業のプロジェクトに参画しており、開発推進に留まらず企画フェーズから内製化支援を複合的におこなっています。
一つは、情報システム部門におけるシステム開発の推進や、AI・データ利活用プロジェクトの推進です。来年度の計画の具体化やシステムの基本計画策定など、プロジェクトが始まる前の「企画フェーズ」から深く入り込み、社員の方々と伴走してシステム開発を支援しています。
もう一つは、クライアントの業務部門まで入り込む改革です。情報システム部門と業務部門の間にある壁を解消する橋渡しとなる、「ビジネスアナリスト」の役割を組織内に立ち上げるプロジェクトを進めています。これは、システムがわからない業務部門の要望を整理し、情報システム部門へ適切に繋ぐという、内製化支援の思想を体現する取り組みの一つです。
松土さんは現在、事業部の戦略立案などをはじめとする事業づくりにも関わっていらっしゃると伺いました。具体的にどのような活動をおこなっているのでしょうか?
あらゆる課題に対して包括的なソリューションを提供できる組織を創るため、事業責任者と戦略立案、戦略実行において足りないピースの採用、外部企業との提携まで、多角的に動いています。
現在は、システムコンサルティングを軸にしていますが、事業における目標はクライアントの課題解決を全方位で支援する組織になることです。将来的には、システムコンサルタントと戦略部門が連携し、クライアントの曖昧なご相談から具体的な課題解決まで、システムのみに限定しない多角的なアプローチで一貫した支援を提供する組織を目指します。この目標達成のため、不足しているリソースを補うべく、採用活動にも積極的に取り組んでいます。
加えて、外部企業との連携による専門性の強化も進めています。直近では、セキュリティ、AI活用、モダナイゼーションに強みを持つ大手企業と協議し、社内に専門部隊を育成することで、クライアントの多様な課題に対応できる組織体制を構築しています。
入社されてから、気付いたレバテックならではの魅力はありますか?
結果に至るまでのプロセスを重視する点や、徹底した長期的な育成視点は、他社にはないレバテックならではの魅力だと感じています。
レバテックの評価は、プロジェクトマネジメントやチームワークといった、本質的なコンサルタントの行動に焦点を当てられています。さらに、「この人はこの経験が不足している」という点に対して、それを経験できるプロジェクトを考えてアサインするなど、徹底した長期的な育成視点に基づいたアサインを実施しています。この育成視点こそが、結果的にコンサルタント一人ひとりをオールラウンダーに育成し、組織全体の競争力向上に繋がると考えています。
なぜレバテックでは、これらの評価制度や育成方針を実現できるのだと松土さんは考えますか?
レバレジーズの強固な経営基盤と、定性面を重視した採用方針があるからだと考えています。
未上場で資金調達をおこなわない独立資本経営で潤沢な資金力があり、コンサルティング部門単体の売上に依存するのではなく、他の事業が安定的に高い収益を上げているため、新規事業の成長と人材育成という長期的な投資を優先できる。大手ファームでは実現し得なかった「本質的なクライアント課題の解決」を可能にする土壌がまさに整っているんです。
さらに、利他性が高く、視座の高い優秀な人材が多く採用できていることも要因だと感じています。これは、レバレジーズが単に経歴やスキルだけでなく、「信頼」や「情熱」といった定性面を重視して採用しているからです。自己の利益だけでなく、組織の成長のためにチームで切磋琢磨する文化が根付いており、それを体現できる人材を毎年何百人も採用できている。
だからこそ、会社も個人を信用して惜しみない人への投資ができるのではないでしょうか。実際に、同年代の尊敬できるメンバーも多く入社しており、刺激を貰える毎日です。この組織の健全性と無限の可能性は、レバレジーズの組織体制ならではだと痛感しています。

さいごに
最後に、入社を検討しているコンサルタントの方々へ、メッセージをお願いします。
大手ファームで身につけられるロジカルシンキングとプロジェクトマネジメントは、汎用性の高い重要なベーススキルです。しかし、真の安定は会社名ではなく個人の実力によって築かれると私は考えます。
レバテックには、そのプロフェッショナルな実力をさらに最大化できる環境があります。
「常に成長したい」という挑戦心と当事者意識を持つ方にとって、レバテックはこれ以上ないフィールドです。単なるクライアントワークの枠を超え、事業戦略・組織創りの最前線を担っています。
新しい取り組みを提案すれば、「やってみて」と挑戦を後押しするカルチャーがあり、それを支える潤沢な資金力と、成長を適切に評価する独自の評価制度が整備されています。コンサルタントとして実力をつけ、自らのキャリアを主体的に形成したいと考える方にとって、レバテックは「経営視点」と「コンサルタントとしての経験」を得ることができる最良の環境です。
現在、レバテックのコンサルティング部門は、未完成な組織。だからこそ、今までのコンサルタントとしての経験と知見を活かし、事業・組織創りの最前線で活躍できます。ぜひ、私たちとともに「日本を、IT先進国に」する挑戦をしていきましょう。
▼現在募集中のコンサルティング事業部の求人はこちら!▼